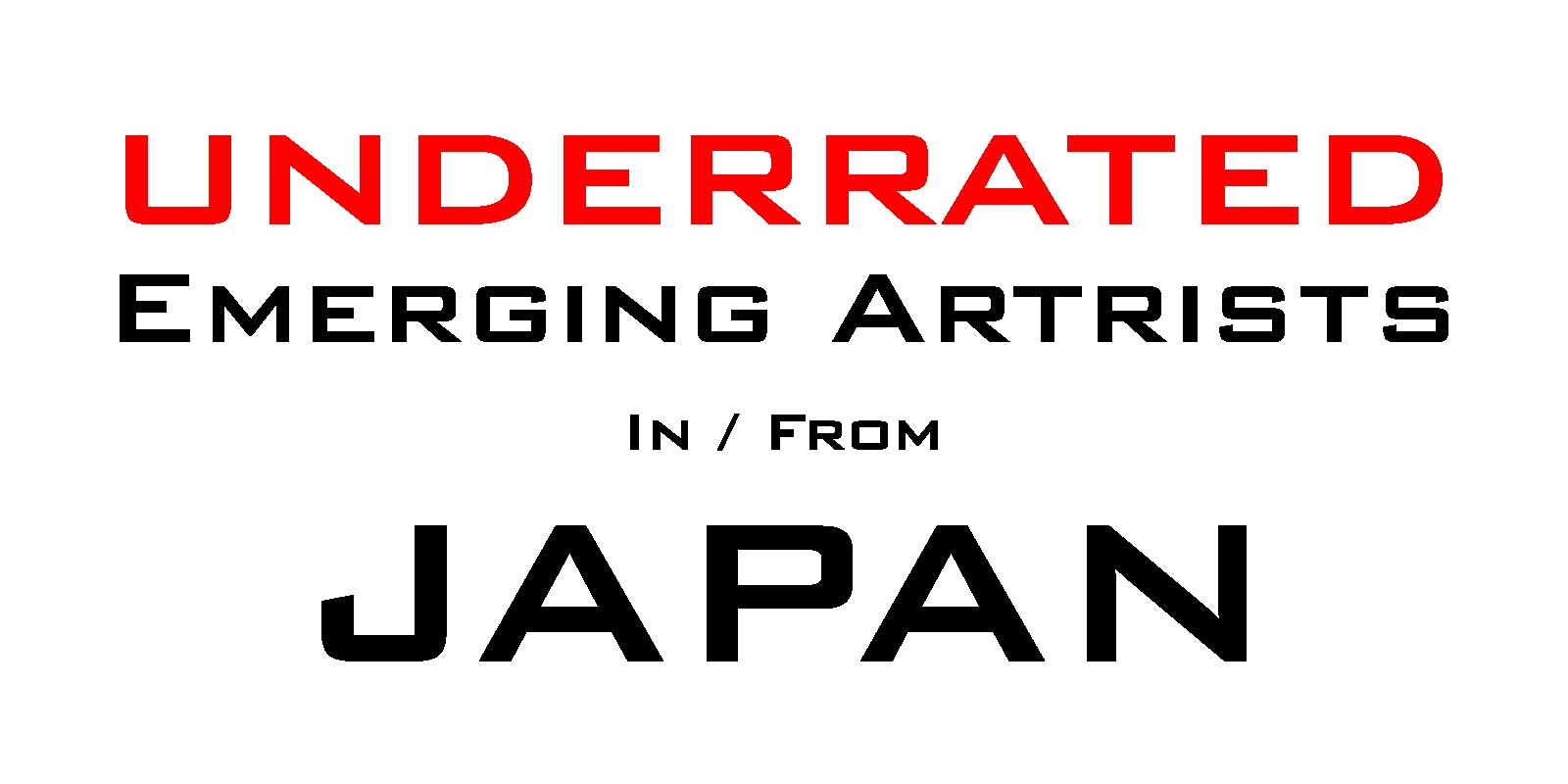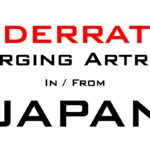日本の文化コンテンツは凄いんだよ。奈良時代から。
日本のコンテンツが凄いのはもう奈良時代からずっとで、外国にも日本美術のコレクターはいっぱいおるし、日本美術コレクションがウリの美術館もあるし、浮世絵の程度の良いやつはオークションで凄い値段つく。
映画だって高く評価されてきた。そしてついにジブリもん以外のアニメやマンガのアウトバウンドビジネスが本格化した。
日本のアニメやマンガの凄さや魅力を支えているのは膨大な数のクリエイター。アマチュア、プロ、フルタイムプロ。ファンの数も凄まじいし、目は肥えているし、ファンが良いものを発掘して人気に火がつき、上の方に上がっていくという回路も一つの成功パターンとして確立している。個々の作品について頼まれなくても熱く語る人の数も膨大。
では日本の「現代アート」はどうだろう?
ブームだブームだと言われている日本の現代アートはどうか。
絵を描く人の数はやはり膨大だし、スカルプターもそれなりにいる。フォトグラファーも多い。しかしその「数」が力になっていないような気がしてならない。有力コレクター(ということになっている人たち)は都心の有力ギャラリーにオススメされたものを買うだけで、自分の目でアーティストを発掘してはいないように思える。
だが都心有力ギャラリーが日本全国のアーティストを悉皆調査してその中から精鋭をよりすぐってご紹介しているようには到底思えない。リソース的にも無理だし(VOCAやCAFや岡本太郎や群馬青年や五美大展でスカウティングしているんじゃないかと思うが)。
その都心勢中心で盛り上がっているように見えるのが昨今の「現代アート」ブームだが、52歳のおじさんには「こういうの今までに何度も見たやつ」という光景だ。
80年代後半の「バンドブーム」
90年頃の「ジュリアナ東京ブーム」
90年代半ばの「渋谷系ブーム」
90年代末の「ガーリーフォトブーム」
00年代の「クラブDJブーム」
他にも「ブーム」はいくらでもあった。出てきては消える。マスメディアを利用してブームを演出して楽して金儲け。文化としてはほとんど残らない。コアな人たちはブームの前からやっていてブームが終わっても続けている。安易な「ブーム」商売ではない、地に足のついた創造の生態系は何かを考えて、それを目指していくことが大事だろう。
山脈になっていない。豊かな生態系が生まれていない。
日本国内の有力な現代アート公募の審査員がごく狭い人脈に集約されている(ように見える)のが問題としてかなり大きいと思う。また鷲田めるろ先生ですか、みたいな。
どれだけ公正公平に審査していると主張しても、個々人の好みは必ず入り込む。
20世紀に日本各地で結成された洋画の同人展も無数にあるけれども、あちらはあちらで長老制の限界集落みたいになっているところばかり(に見える)。
若手支援と称して駆け出しに50万円100万円を渡してこれで何とかしてこい、で、35歳を過ぎると極端に公募が減る。もはやどっかの学校に籍だけ置いてCAF賞に出すしかないのか、みたいな有り様だ。35歳といえば現代アートのキャリアでは(最も順調な人で)ようやくMid Careerの位置に片手が取り付けるかどうかの段階だが、そこで梯子が消える。35を越えたシリアスな日本の現代アーティストが生き残ってキャリアを伸ばすにはロンドンやNYやLAやベルリンに拠点を移して向こうのグラントやフェローシップを取るしかなくなる。
アホだ。間違いない。
色々な問題が複合して、せっかくの膨大な人的リソース(何度も言いたいんだがスレッズに流れてくる日本各地の、中央では知られていない画家たちの絵のレベルは非常に高いと思う)が生かされず、裾野があって頂上がある大きな山脈とその生態系になっていない。
これについて個人で出来るアクションとして、ウェブマーケティングと国際公募を活用して直接外国に出ていくルートの藪漕ぎをしているけれども(1日平均で3-4件の公募をチェックすることを3年やっているので、これまでに見た外国の公募は3000は軽く超えているはず)、並行して草の根のアーティストランの公募が、今の100倍くらい国内に存在するようになると、山脈が形成されるのではないかと思っている。
少なくとも現在の日本の現代アートの生態系が「これで100%上手く行っている」 「全ての才能を適切に支援出来ている」 「アウトバウンド戦略は完全に成功している」 「このままで何の問題もない」と言い切れる人はいないはず。欧米では中国と韓国のアーティストの方が遥かに成功している。国粋主義者として悲しくなってくるくらいに差がある。