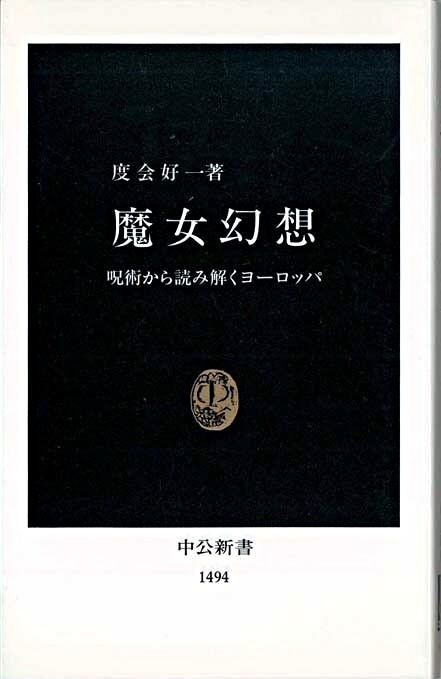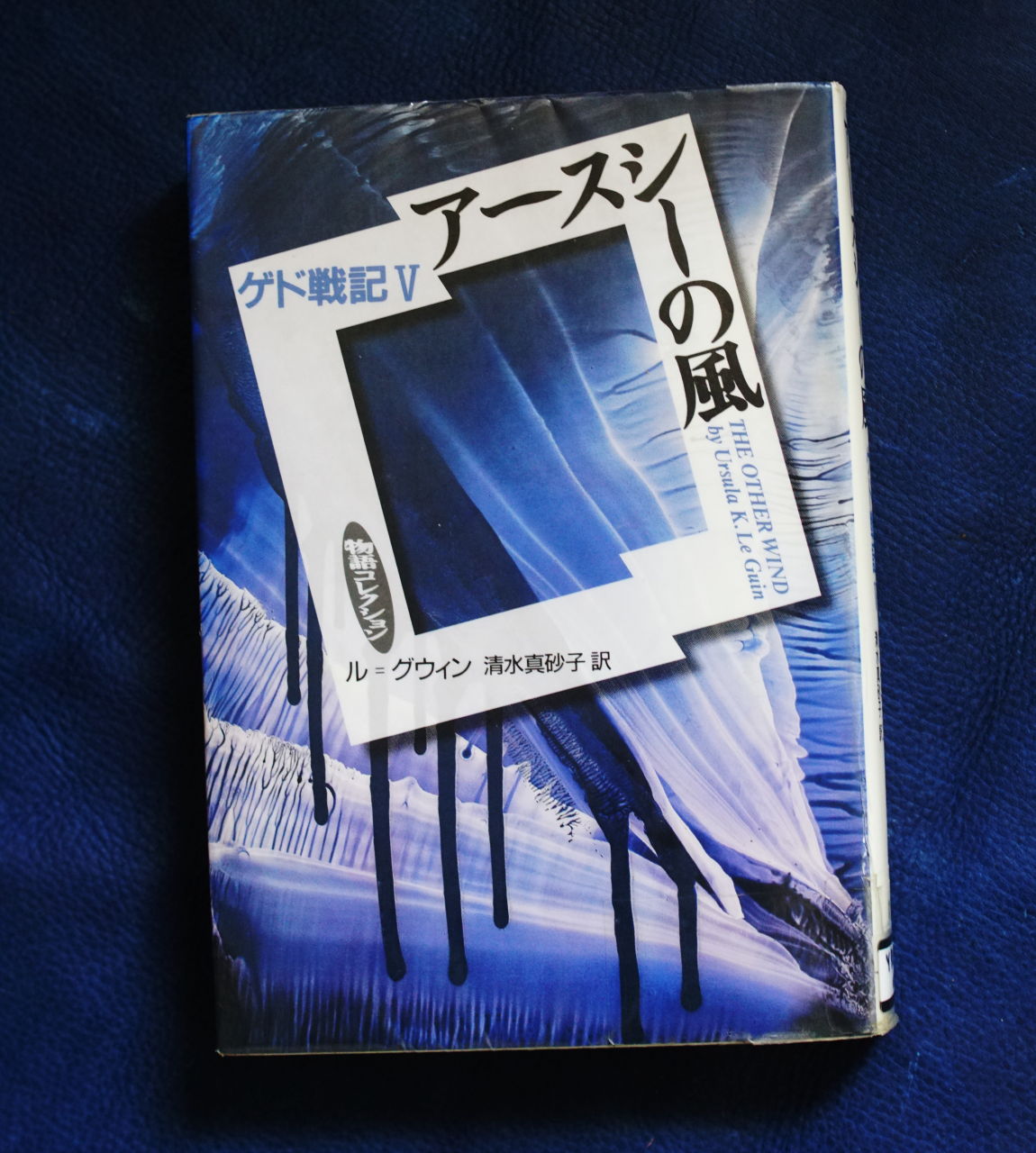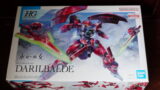トータルでの評価
・水星の魔女論ではなく魔女とケア論として読むべき。水星の魔女の読み取りはかなり怪しい(後述)し、水星の魔女とはあまり関係ない現代文学についての議論の方が遥かに多い。
・文芸批評は実証性や正確性、精密性より面白さが大事と割り切れ。
・「水星の魔女」における魔女概念が日本のアニメや漫画やラノベにおけるそれではなく、むしろ「山姥」に近い(ヨーロッパの魔女概念はそもそもそっちだから)という指摘とそれを鍵にした分析は労作。「水星の魔女」放送終了後に「結局魔女って何だったんだ」と文句を言っていた人たちは、とりあえずこれを読め。
・「ゆりかごの星」と15話エンディング後のデリング設定開示シーンを見落とした水星の魔女論はありがちな事故。小川公代の論考もそれをやらかしている可能性を頭の片隅に置きつつ読んだ方が良い。
個別の疑問点
第1章では魔女の歴史を概観するのだが、依拠しているのが1970年代にフェミニズムの理論家たちが書いたもの2冊なので、そもそも資料として古いし実証的な歴史学の研究でもない。フェミニズム文芸批評に極めてありがちな書き方ではあるが。
せめてこちらも読んでからにした方が良かったのでは
第3章ではデリングをネオリベ的企業家として紹介しているが、15話エンディング後のラジャンとミオリネの会話を見落としたのだろうか? フェミニズム文芸批評家がビジネスや中高年オヤジについてdpi72くらいの低解像度なのはお約束とはいえ、小川公代によるデリングの理解は極めて表層的に思える。
第4章、プロスペラはエリクトとコミュニケーションできる方法を探していたのではなく(17話でエアリアルとプロスペラは会話している)、エリクトが活動できる領域を全地球に拡張しようとしていたのでは?
第5章、エリクトの声が聞こえるのはスレッタだけではないはず。プロスペラの他、エラン4も聞いていなかったか? 小川公代によるSFの設定部分の理解はここに限らずかなり危うい気がする。パーメットスコアについてもパイロットの体内に入るパーメットの量という、5月頃によくあった考察をそのまま書いているのだが、パーメットスコア8まで上がったエアリアルがスレッタ(=パイロット)無しで動けるという公式設定(これも小川は注で紹介している)との整合性が取れない。
スレッタが強かったのはエアリアルと同期できたからという理解もかなり浅いのではないか。キャリバーンに乗り換えてエリクトやカヴンの子たちのアシストが無くなった状態で、エアリアル改修型とガンドノード群の猛攻を凌ぎきったのは、スレッタがそもそもパイロットとして作中最強レベルであることを示唆していないか。グエル・ジェタークやシャディク・ゼネリでは無理だったはず。
第6章、ミオリネが株式会社ガンダムを設立したのは戦争シェアリングを解体するためではなくスレッタを守るためでは? 第7話の「意地じゃない!」というセリフが友情なのか恋愛感情なのかは不明なれど。
第7章 スレッタってそんなに人の話を丁寧に聞く子だったろうか? スレッタは20話でノレアが暴れたあたりでケアラー的な属性を獲得したように思う(小川公代は別の本でも自分のテーマであるケアの倫理にあらゆるものを結びつけ過ぎる印象はある。文芸批評系の人の手癖かもしれない。ダメとは言っていない)。
魔女についてのリサーチ不足
魔女っ子アニメの言及が花の子ルンルンとときめきトゥナイトだけというのも物足りなさすぎる。ミンキーモモなどスタジオぴえろ作品、セーラームーン、プリキュア、まどマギ、ウテナなど全部スルーで水星の魔女で魔女論を展開するのは非常に疑問。特にウテナと水星の魔女の関連性は散々指摘されているので。
『花の子ルンルン』や『魔女っ子メグちゃん』などのポップカルチャーによって、欧米の「魔女(witch)」観は部分的に”翻案”されてきたといえるが(*2)、現代魔女の円香、現代魔女術実践家の谷崎榴美によれば、日本の魔女文化は「愛らしい魔女っ子や妖艶な美魔女」として継承され、「蠱惑的側面に偏ってしま」った(*3)。
欧米の魔女はむしろ、日本文化における〈山姥〉に近いのだという(*4)。山姥は「老女」と形容されるなど醜怪なイメージと結びつくが(*5)、欧米の魔女は、美醜の二面性を持ち、必ずしも「愛らしい」「蠱惑的」というわけではない。
『水星の魔女』の登場人物のなかでもっとも魔女的な存在のプロスペラは──そして「呪い」のモビルスーツのパイロットに成長するスレッタも──善悪の二面性を有する魔女であり、かつ〈山姥〉であり、その点で”魔女っ子”アニメとは一線を画している。
同じように、魔女の文学の系譜で1960-70年代のエコフェミニズムの強い影響を受けたファンタジー小説を一切見ていないのも極めて不満。
その辺の話は以前にここでまとめた
せめてル=グウィンの『アースシーの風』とマキリップの『妖女サイベル』は見る程度の手間をかけて欲しかった。
ところでスレッタは魔女だったんですか?
以下はあくまでも私の個人的解釈。
「水星の魔女」は復讐や懲罰ではなく修復の物語であろうというのはこちらに書いたのだが
スレッタはグエルVSミオリネ、ミオリネVSデリング、シャディクVS株式会社ガンダム、最後はプロスペラと議会連合など、放っておくとどちらかが潰れるまで戦っていたはずの対立を最後まで調停し続けた。
よく水星の魔女が何も解決せずに大団円したと批判されるのは、これまでのガンダムで対立構造はどっちかが死ぬか両方死ぬかで懲罰・決着の形で白黒つけてきたものを、有耶無耶だけど死人は出ない形での調停に置き換えられているからだ。
小川公代の論考ではこれを魔女の女性性からケアという原理を引き出してスレッタをケアする者として解釈しようとしていたけれど、立場的にもスレッタは魔女(ヴァナディース機関のメンバー)ではなく魔女プロスペラによって生み出されたガンダムの一部(リプリチャイルド)なので、carerより妖精alfのconciliatorとして読んだ方が良いような気がする。
ガンダムルブリスが魔女たちによって開発されていたことを考えあわせると「平和の魔法の妖精Gandálfrith」(魔法 gand, 妖精 álfr, 平和 frith)なのかなと思いました。