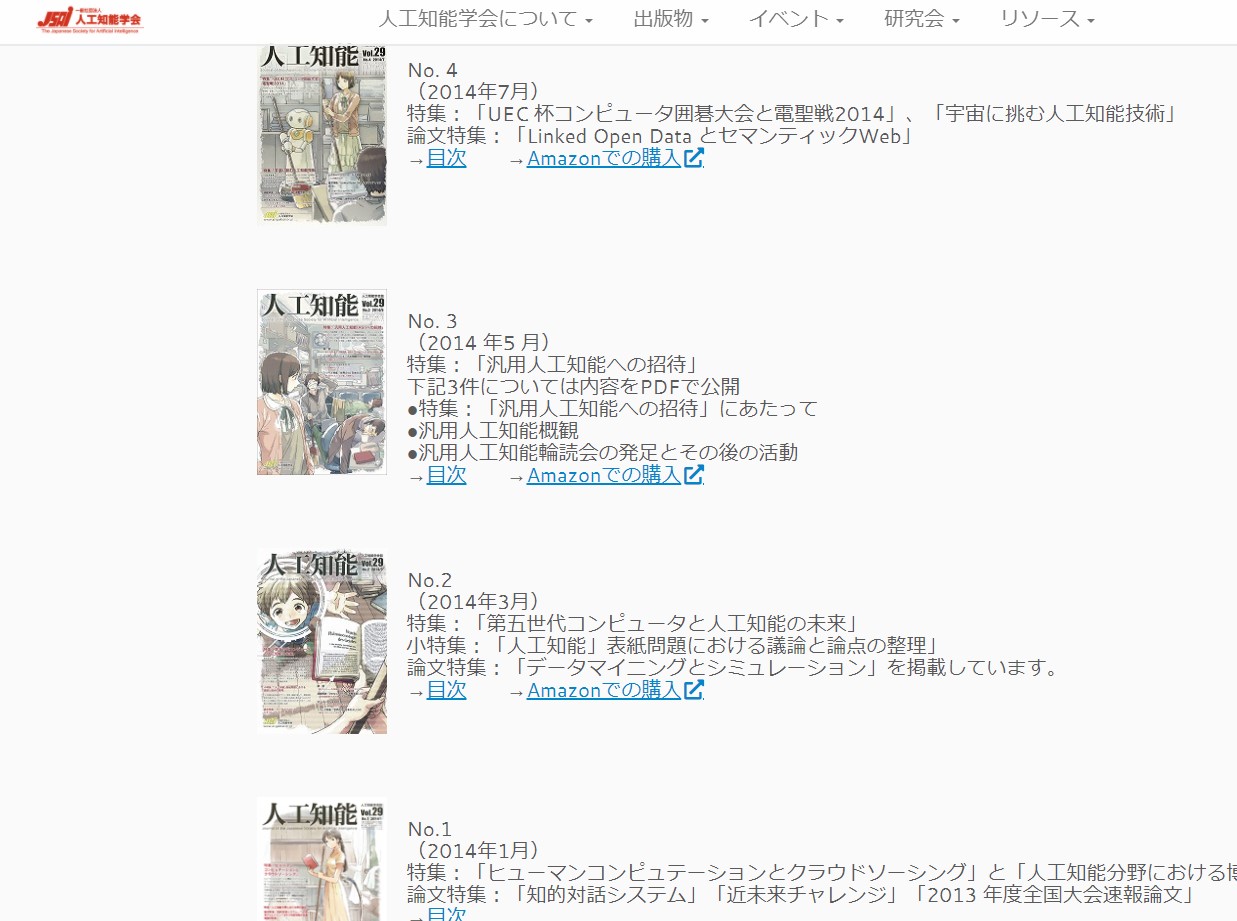春先に、「お掃除をする[見た目が日本人女性に似た]アンドロイド」を学会誌の表紙絵にして騒ぎになった人工知能学会。
第2弾で「このアンドロイドはヘーゲルの『精神現象学』についての論文を読んでいた」というオチが来て終息したと思いきや、まだまだ続く連作だったそうで、第3弾が「女性に叱られて研究室の掃除をさせられる男子院生(多分)」、第4弾は「男にも女にも見えないお掃除ロボットと並んで箒の柄のようなものを持つ(先端は隠れている)女性」でした。
で、その連作をフェミニズムを研究する大学院生が表象文化論学会というところで自分の学会報告のマクラとして使ったのが先週土曜日。
前置き長かったですが、このリンクは、その学会報告へのツイッター上での感想です。
「フェミニズムの観点から人工知能という一般的問題にアクセスするのであれば、人工知能学会の表紙という特殊な素材は必要ないと思われる。少なくともフェミニズム理論はとっくにそのような地点は通過しているはずなので、じゃああとは啓蒙が足りないのか、というそういう話なのだろうと思う。扱う切迫性のないもの(新しい問題を見つけられないもの)を「余裕」(五分程度)で切り捨てる態度というものは、むしろフェミニズムのこれまでの歴史に対する冒とくではないか、とすら思った。」(逆巻しとね)出典
私があかんなあと思うのは1点。
フェミニズムの理論が、お掃除ロボットの疑似ジェンダーの是非のようなテーマはとうの昔に論じ尽くしているのに、フェミニズムビジネス関係者以外には全然伝わってないじゃないの、と嘆いておられるんですが、あのな、
「研究室で作った試作品がいかに華麗に動作したって、それをコンシューマ向け製品として完成させて市場に問わないと、アカデミアの外では何をやったことにもならんのよ。」
新しい理論が出来たらそれを使った試作品を使ってフィールドで実用試験して、そっからフィードバックもらって改良するPDCA。それをやらずに「こんなの我々が10年前に作った試作品で解決したはずの問題ですよ」と嘯くのは、愚か者です。ちゃんとプロダクトかサービスに落とし込んでいかないと。
だから人文系の研究者はバカにされるのよ(私も人文系ですが)。