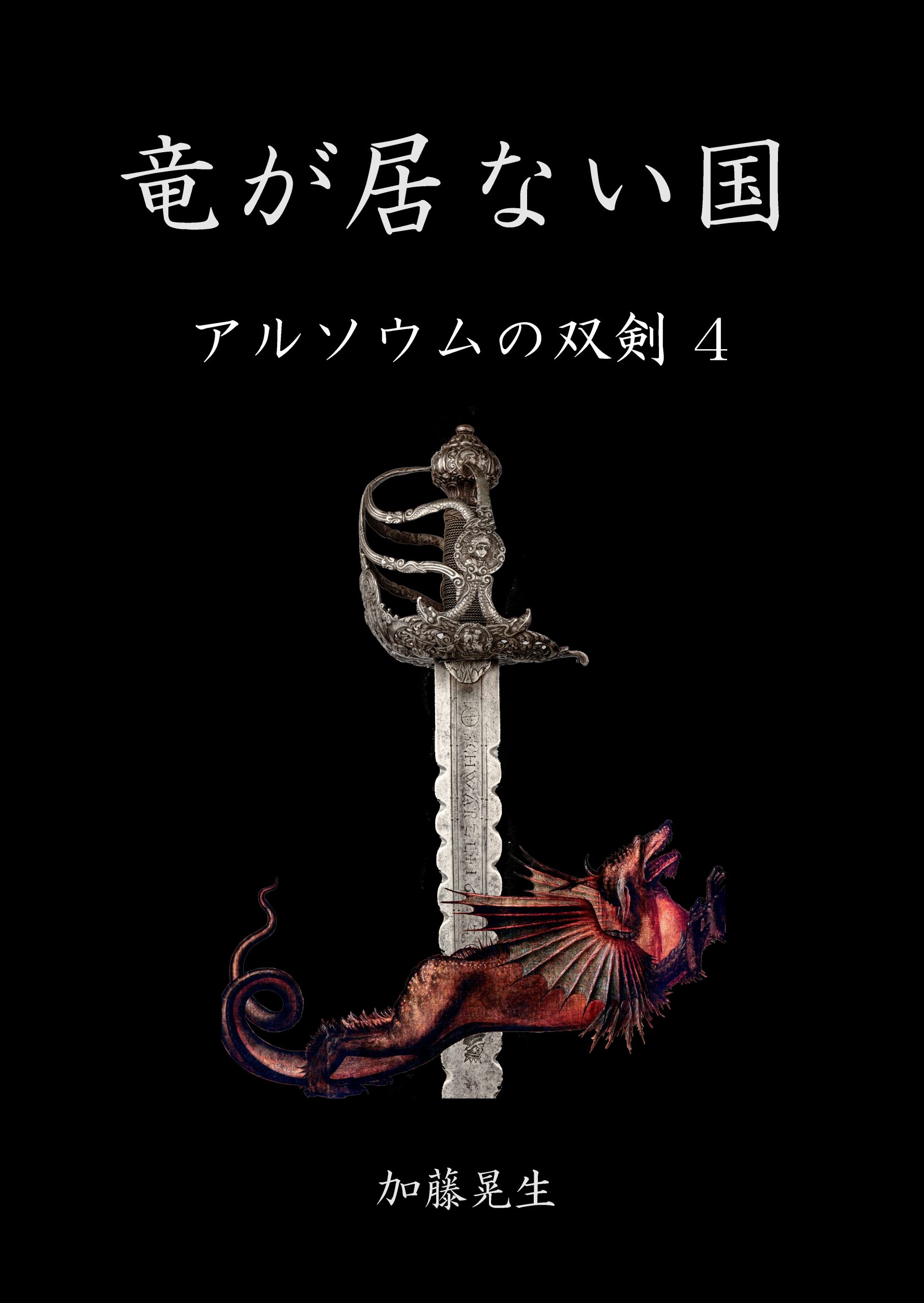批評というものについての理解が1960年代以前の古き良き作家論や作品論の段階で止まっているような(しかし私よりかなり若い)小説家や編集者を発見するのに、さほどの苦労を要しないということに戸惑っている。
こないだ立教の文芸思想専修の先生と話したときに、今の学生は本当に本を読まないと苦笑いしていたが、コンテンツとしてゲームやアニメやマンガばかり摂取するのは、良いと思う。何の問題も無い。
特にゲームはこれから一番(市場規模も創作の多様性も)伸びる文芸ジャンルだと思っている。
問題は、場所はどこであれ他人に何かを教える・語る立場に立つような人間ですらバルトやフーコーやサイードやボードリヤールなど、文学部系の修士論文でこれ踏まえて無かったら恥ずかしすぎるでしょというものを、おそらく知らないことだ。
これは
「せんせー、チャック開いてますよ」
どころではない。
「せんせー、ズボン履くの忘れてますよ」
レベルのことだと個人的には思うのだが。
フェミだポモだポスコロだカルスタだクレオールだと、ともすると揶揄されがちな70-90年代の文芸批評のツール群ではあるが、それぞれに重要な示唆があったから、なんだかんだで批評の常識に属するものになった。
だが、こういう知識を一切持たない方々がどういうわけか指導的な(あるいはムラの青年団長的な)ところに居て、俺の経験、私の考えを語っているようなものが、どうにも多い。
それを可能にしているのが、日本の大衆文芸の書き手の間に今も(おどろくほど)根強く残る「商業出版で紙の本を出している人が偉い」という感覚ではないか。
あのせんせーは何冊も本を出していて文芸誌にもたまに出てくるから偉いに違いないというやつだ。権威に訴える誤謬である。
だが、そうした俺論は結局のところ俺の権威を補強する方向に行きやすい。こうすればあなたも紙の本が出せる可能性があがります。売れなきゃ意味がありません(そういうご本人もベストセラーなど出したことが無かったりする場合が多いのだが)。
何故そういう立論になるのか。
そこにしか青年団長の論を支える梁が無いからだ。鈴木芳樹がこの世に残していったほとんど唯一のものである「せめて単著を出しやがれ。そうでもなけりゃ相手にする気にゃなれん」(栗原裕一郎との論争において発言。なお栗原はこの2年後に単著『〈盗作〉の文学史』(新曜社2008年)を上梓している)というフレーズと通底するものがあるが、つまりはマウンティングである。しかも限りなくこの世の底の辺りにおける。
もちろんそんな俺論も言論の自由だから、多いにやったら良い。「持論を展開」というあれだ。
だが、そういう俺論ばかりが流通する言説のありようが、大衆文芸の創作の多様性や自由度を制限する方向に作用しないかが、若干だが心配になった。
これを二言でまとめると、こうなる。
「個々の小説家の経験談を読むのも意味無しとはしないが、一通り目を通したら文学研究の(なるべく新しめの)入門書であるとか、表象文化論や各種批評の古典を読む方が時間の使いかたとしては有意義なのではないか。そして何よりも、創作論の摂取に時間を割くよりは創作そのものに時間を使った方が良いのではないか」
|
|
|
|


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0a0ae637.10e48172.0a0ae638.5577ea7e/?me_id=1213310&item_id=20420495&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4256%2F9784480074256_1_4.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0a0ae637.10e48172.0a0ae638.5577ea7e/?me_id=1213310&item_id=20248220&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2537%2F9784909812537.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)