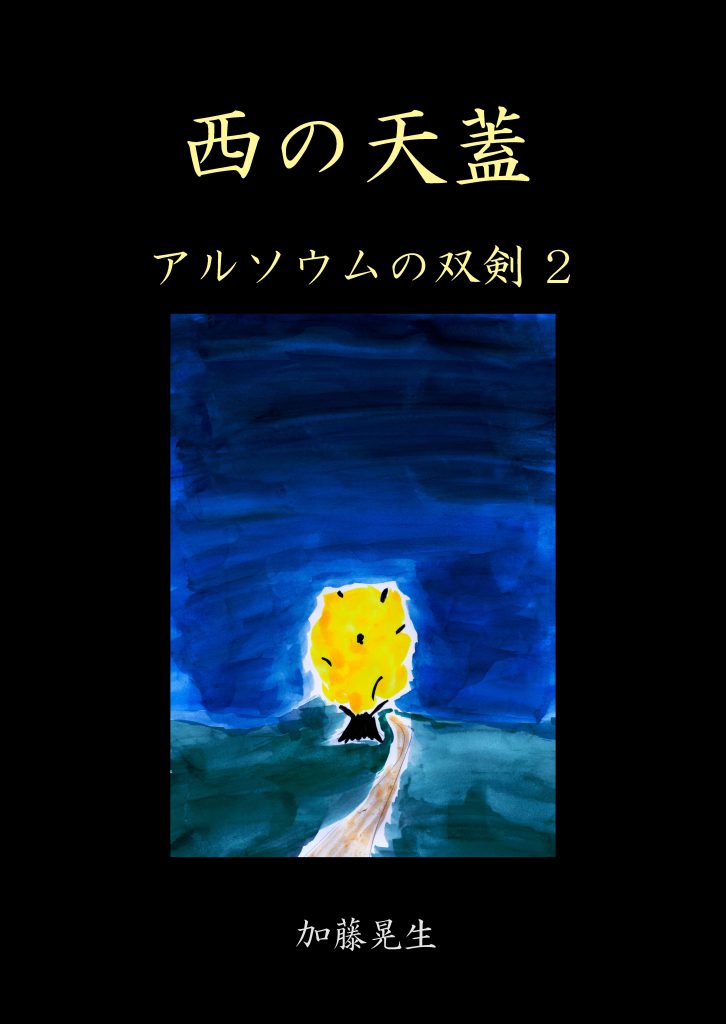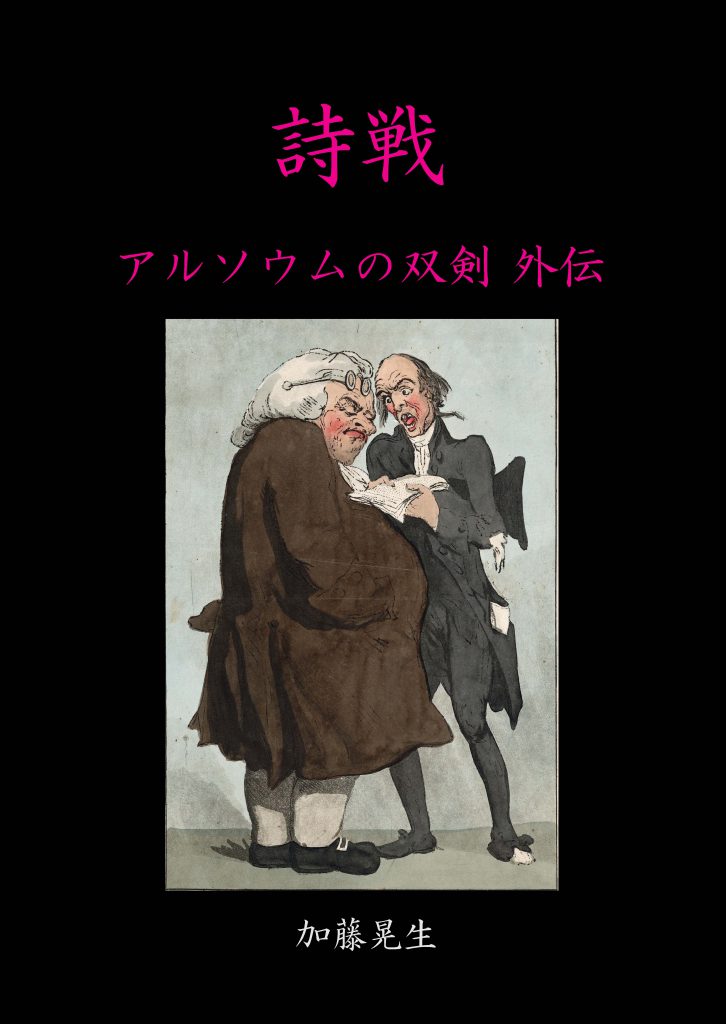赤澤智『人生に行き詰まった僕は、喫茶店で答えを見つけた』(祥伝社, 2020)を読了したので、書評です。
ですが、最初に私と赤澤さんの関係を書いておかないとアンフェアなので、まずはそこをざっと説明しますね。
赤澤さんは立教大学軽音楽部で4年か5年くらい上の先輩です。同じ時期に在学していたわけではないのですが、合宿やライブなどのイベントでお見かけする方でした。
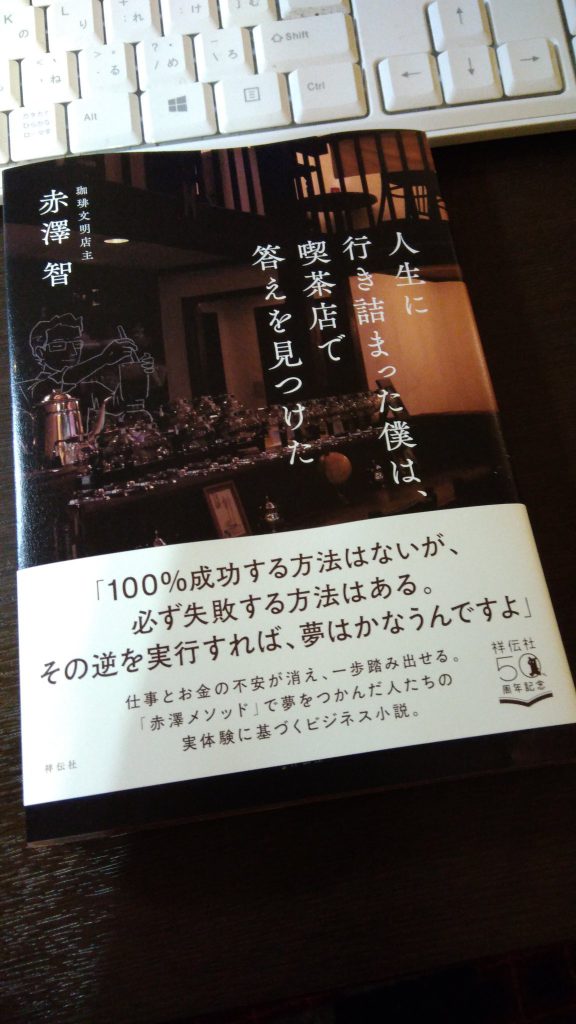
その赤澤さんが白楽でカフェをやっておられると聞いたのは2007年のことです。
当時私が関わっていたハワイの航海カヌーのプロジェクトでたまたま知り合った方がやはり立教軽音の先輩で、赤澤さんの同期だった、というご縁です。
それで必然的に赤澤さんのカフェのウェブサイトやブログを拝読しました。
特にカフェ開店までのブログは(膨大な量でしたが)一気読みしました。
その後はFacebookやTwitterでもお付き合いいただくようになったのですが、赤澤さんは常に私の数少ない「人生のお手本」の一人でありつづけています。私がオリジナルの男性用育児バッグをデザインして売り出した時も、教科書にしたのは赤澤さんの開業ブログでした。2017年には私が(コンサルタントとして)立ち上げた福祉施設でコーヒー講座をしていただいたこともあります。
そういう関係です。
もちろん赤澤さんからも、加藤くんレビュー書いてねと声はかけられています。しかしながら、赤澤さんも私がどういう人間なのか、かなり詳しく知っておられますから、「褒める書評にしろ」なんてことはおっしゃいません。
それでは改めてこの本です。
どんな本なのか。
この本には三つのレイヤーがあると思います。
一番上には「小説」というレイヤー。これは、文章の形式です。
二番目には「ワンオペのカフェを開業した上で生き残る方法の指南」というレイヤー。これは、小説という形式で書かれている内容です。
三番目、最も根底にあるのは、赤澤さんの思想。これは、「小説という形式でワンオペのカフェを開業した上で生き残る方法の指南という内容を語ることで、赤澤さんが本当に伝えたかったこと」だろうと思います。
私がここで強調したいのは、「ワンオペのカフェを開業した上で生き残る方法の指南」という二番目のレイヤーまでを見て、これは自分には関係無い本だと思わない方が良いよ、ということです。
私見ですが、この本で一番重要なのは三番目のレイヤーです。赤澤さんの思想です。
これは、日本語が読める全ての人にとって、一読の価値がある部分と思います。その理由は後ほどご説明します。
さて、私は大変に傲慢なので、世の自己啓発本の99%はゴミだと思っていますし(そんなもの読むくらいなら聖書や哲学の古典をおすすめだ)、マッキンゼーだろうがBCGだろうが元外資戦コンですという肩書だけで書かれたビジネス書も基本まあゴミで、こんなものを読むくらいなら経営学の研究書を読むわと思う人間です。入山章栄『世界標準の経営理論』良いぞ。
そんな私が、この本は良いぞと、改めて申し上げます。
何故ならば、この本に書かれた赤澤さん自身の大逆転劇、日本社会のかなりの底のところから現在の地位を築き上げるに至ったプロセスを支えた方法論には、かなり高い再現性があると思えるからです。
どういうことか。
世の多くの自己啓発本やらエリートビジネスマンの苦労譚には、本当は一番重要だったのに敢えて全く触れられていない2大要素があります。運とブランドです。
人生、運さえ太ければ他のものは要りません。それくらい運というのは、凄まじい威力を放つものです。
もう一つはブランドです。例えば私が大学で教えていた学生たちが外コンに就職すると、その月から時間単価数万円というフィーをクライアントに請求することが出来ます。もちろん彼・彼女らは十分以上に優秀ですが、そんな単価をいきなり請求してそれが通るのは、トップブランドの中にいるからです。トップブランドでそこそこの営業マンだった人が下位ブランドに転職したら以前のような破竹の快進撃がパタリと止まったなんて話はありふれています。それくらい、ブランドは強い。
運とブランド。この二つの要素を隠したサクセスストーリーなど読むに値しない。
ところがですよ。赤澤さんは本当にロジックと誠実さと思想という、リアルビジネスでは「運」「ブランド」ほどの威力が無いはずの3点セットだけで、この世のほぼ底辺から、誰もが知る名店を築き上げた。
「運」と「ブランド」に頼らない方法論。だから、再現性が極めて高いし、他の分野にも応用が効きます(カフェを開業するキャラと、ライターになったキャラとを出しているのも、そこを伝えたいからではないかと思います)。
そして、先程私が示した三つの武器をよく見てください。
そこには「思想」が挙げられています。
赤澤さんの方法論を学ぶということは、必然的に、赤澤さんの思想を学ぶということになります。
では、その思想とは何か。
「まだ先があるってこと。」(221ページ)
「まだ終わりじゃない。」(222ページ)
これです。
勢いだけで書かれたロックンロールの歌詞でこんなフレーズが出てきたって、私は「またそれかい。その前に禁煙しろ」で終わりにします。
ですが、この本の最後にこれが出てくると「そうですよね、先輩」と思ってしまう。
私はまだ人生に行き詰まってはいないですが、仮に行き詰まり感が出てきたとしても、この本の方法論を使えば、自分の能力から考えて、よほど運が悪くない限りはなんとか出来るだろうと思っています。ある意味でこころの拠り所です。
これを読んでいる方の多くは、人生に行き詰まっていないかと思います。きっとビジネスも順調でしょう。でも、それでもこの本は読む価値があります。私にとってそうであったように。
最後に宣伝です。
私は赤澤さんとは違って、わりとどんな仕事でも楽しくやれちゃう腰の座らない人間ですが、この1年ばかりは「小説を書く」ということに挑戦しています。
2019年の3月8日に突然小説を書き始めて、今日までに長編3本、短編は6本書きました。小さな賞も一つもらって、1年と1ヶ月で60万字以上は書いています。
お仕事にしようという断固たる意思というよりは、自分に小説を書く能力はどれくらいあるかを試してみようという興味本位の挑戦だったのですが、赤澤さんが書いておられるように、続けていたら、短編ですが原稿料付きの発注も入るようになりました。
次は、長編を多くの人に読んでもらいたいなと思っています。
カネは取り敢えず良いから、まずは1000人くらいに読まれたい。
私の長編を読んでくれているのは友人の研究者やビジネスパーソン(だいたい大手の部長級)で、皆さん本当に面白いと言ってくださっているので、多くの人に読まれれば、どこかで次の展開があるだろうと、楽観的に考えています。
もしもよろしければ、こちらとか(長編フリントロックファンタジー・完結済み)
こちらとか(短編ドタバタ喜劇・完結済み)
ぜひ、通勤通学のお供に。