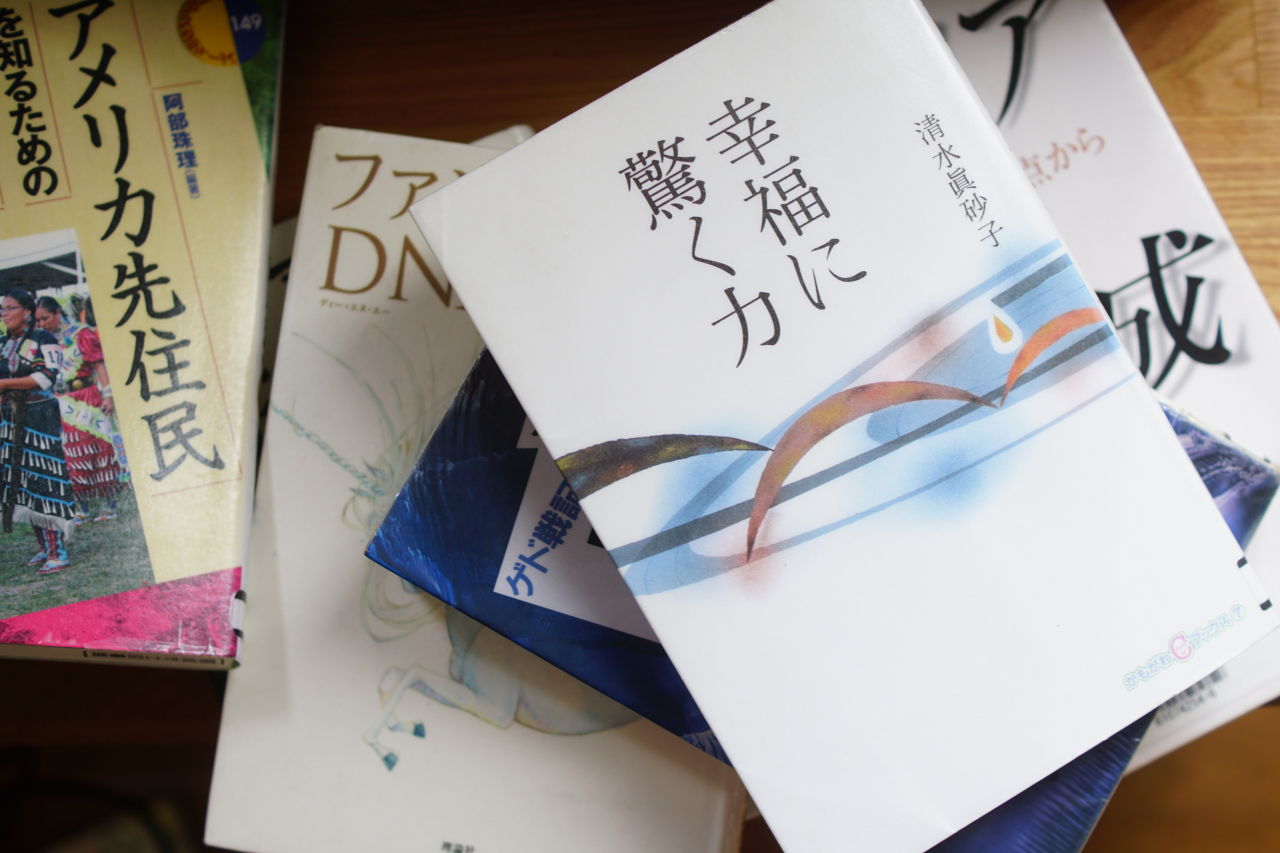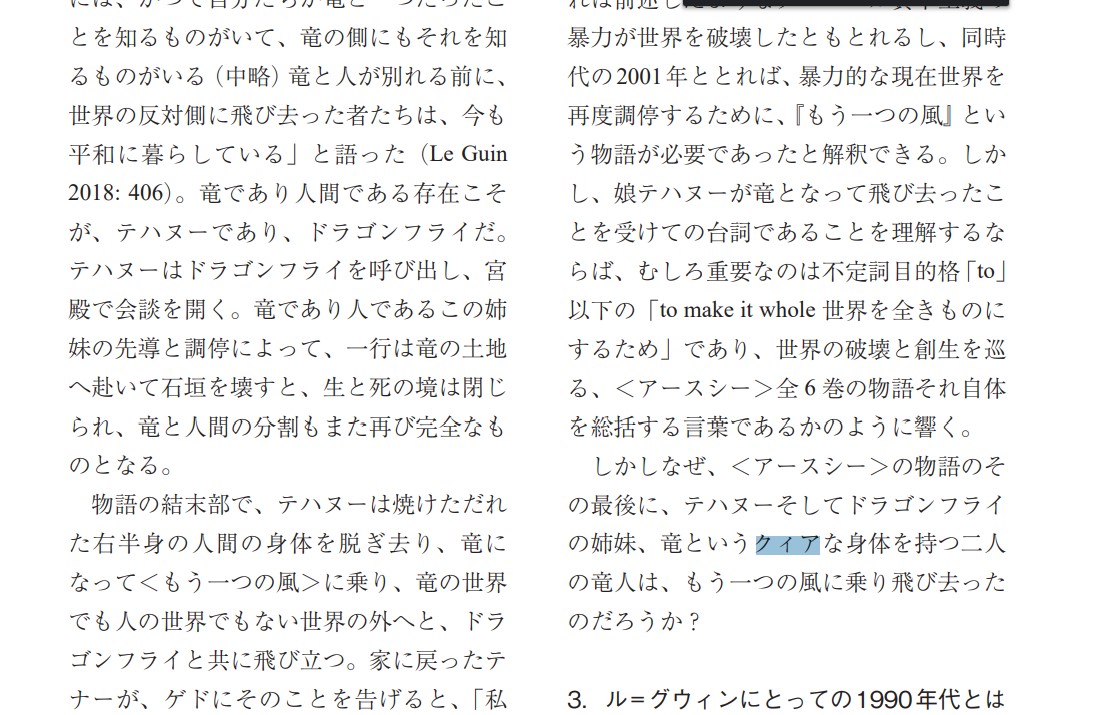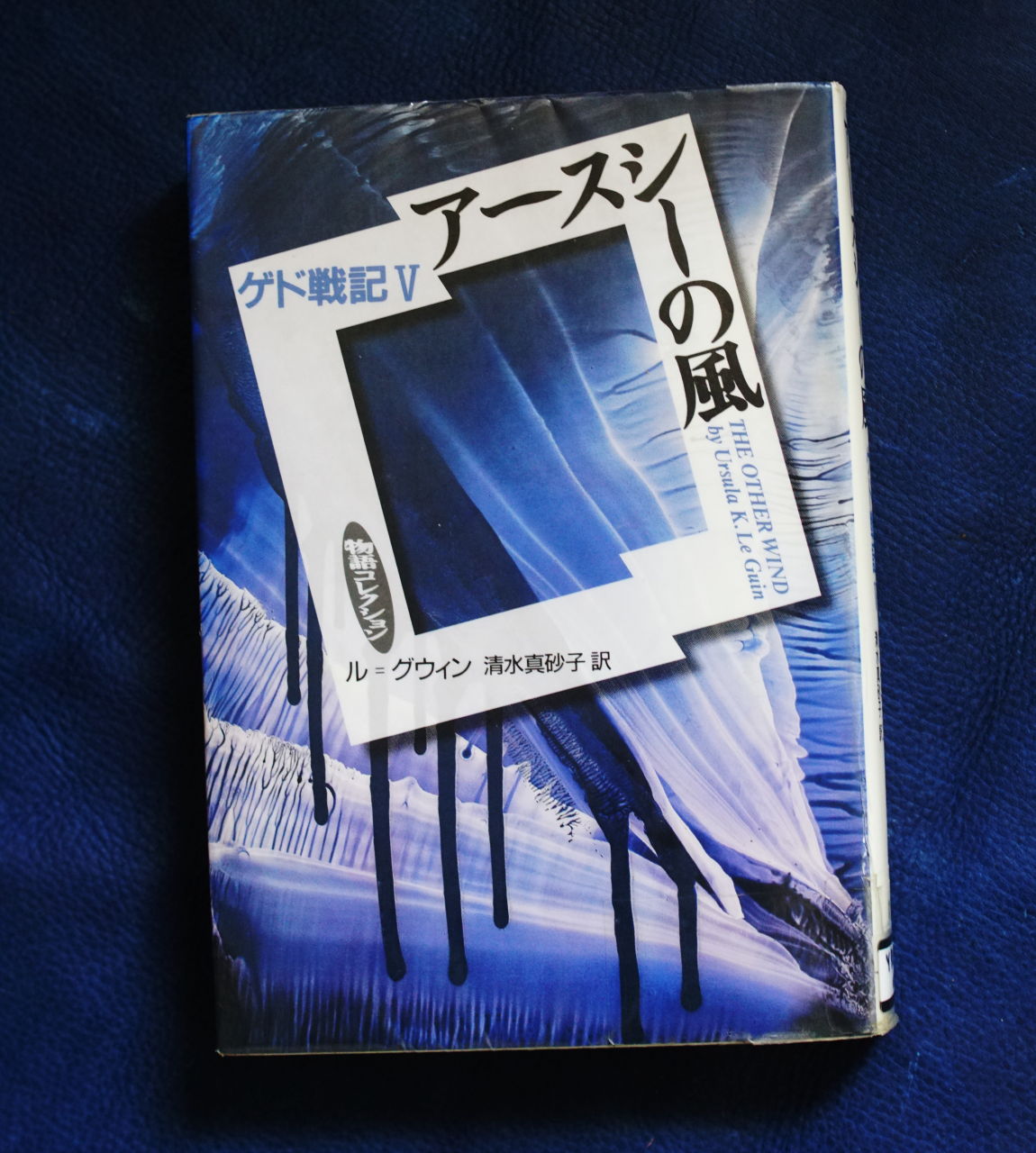翻訳家の清水真砂子の講演録『幸福に驚く力』(かもがわ出版、2006)をついでに借りてきて読んでいるのだが、これが予想外に面白い。
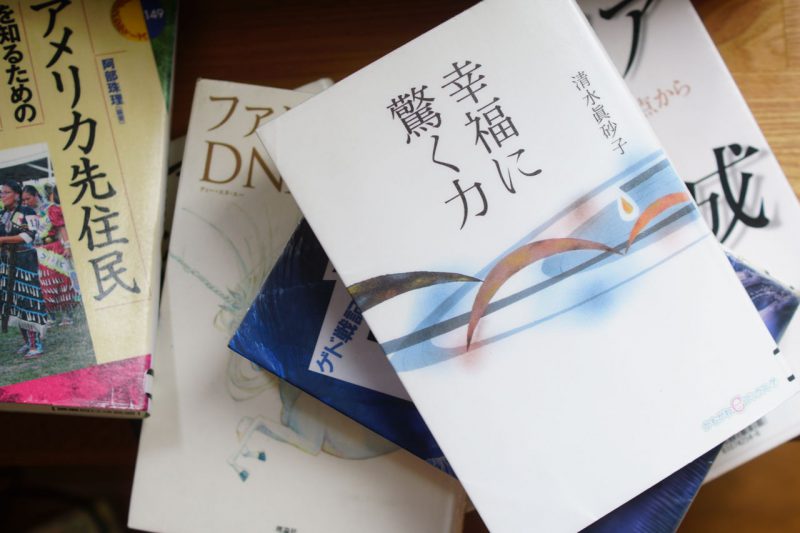
外国は知らないが日本では最近、編集者という肩書の人がやたらとドヤるようになっていて、俺は何百万部売った、私は何十万部売ったというように、売り上げ部数をひらひらさせてウェブ記事で偉そうに語っているのだが、その、まあ限りなく100%に近いところの確率で、
「なんだこれ読むだけ時間の無駄だったわ」
と思わされるものばかりなのです。
私にとってはね。でも彼・彼女らをスーパースター、ヒーローと崇め奉ってせっせとイベントや講座に通うファンがいっぱいいるんだから、それはまあそれでOKよ。
さて、何で部数自慢の編集者たちのドヤトークがつまらんのか、清水真砂子の本を読んでわかった気がします。
清水真砂子は講演の中で、古今東西の人や書名を挙げながら、「もしかしたらこうかもしれない」「こう考えることもできるかもしれない」というように、ごくごく控えめに自分の思考を展開していきます。
この本に出てくる人名を最初の方でリストアップしてみましょうか。
1) ミープ・ヒース
2) ヘレン・ゴードン
3) マヤ・ヴォイチェホフスカ
4) ロナルド・フレーザー
5) 斎藤たま
6) V・E・フランクル
7) ウォルター・スコット
8) ルーマー・ゴッデン
9) E・L・カニグズバーグ
これ、1回の講演で彼女が紹介した人名です。
痛い人文研究者みたいに何の説明もせずにボンボン名前を並べていくのではなくて、ちゃんと「この人はこういうことをした人ですが」とその都度説明を添えています念の為。
私も半分以上は知らないか、読んだことはあっても忘れていた人なので、色々と調べながら読んでいたのですが、調べれば調べるほど面白い情報に繫がっていってきりが無い。
私はこういう読書体験を面白いと思う。
逆に、部数自慢の編集者たちのドヤトークって、出てくる作品名も自分が手がけたものかその周辺にあるものばかりだし、出てくる名前も同じ業界のお仲間の名前ばかりで。
要は「ギョーカイ裏話」です。
それに「こうしたら売れた」というエピソードをくっつけて一丁上がり。そして、控えめに語るのではなくて、とにかく断定的に語る。
視野も狭ければ思考も浅い。いっぱい売っていっぱい納税しているんだから偉い人たちですけど、私にとっては得るものが無い。
でも、ああいうものを好む人のほうがずっと多いのも事実だし、そうやって日々は続いていくんだなと達観はしています。