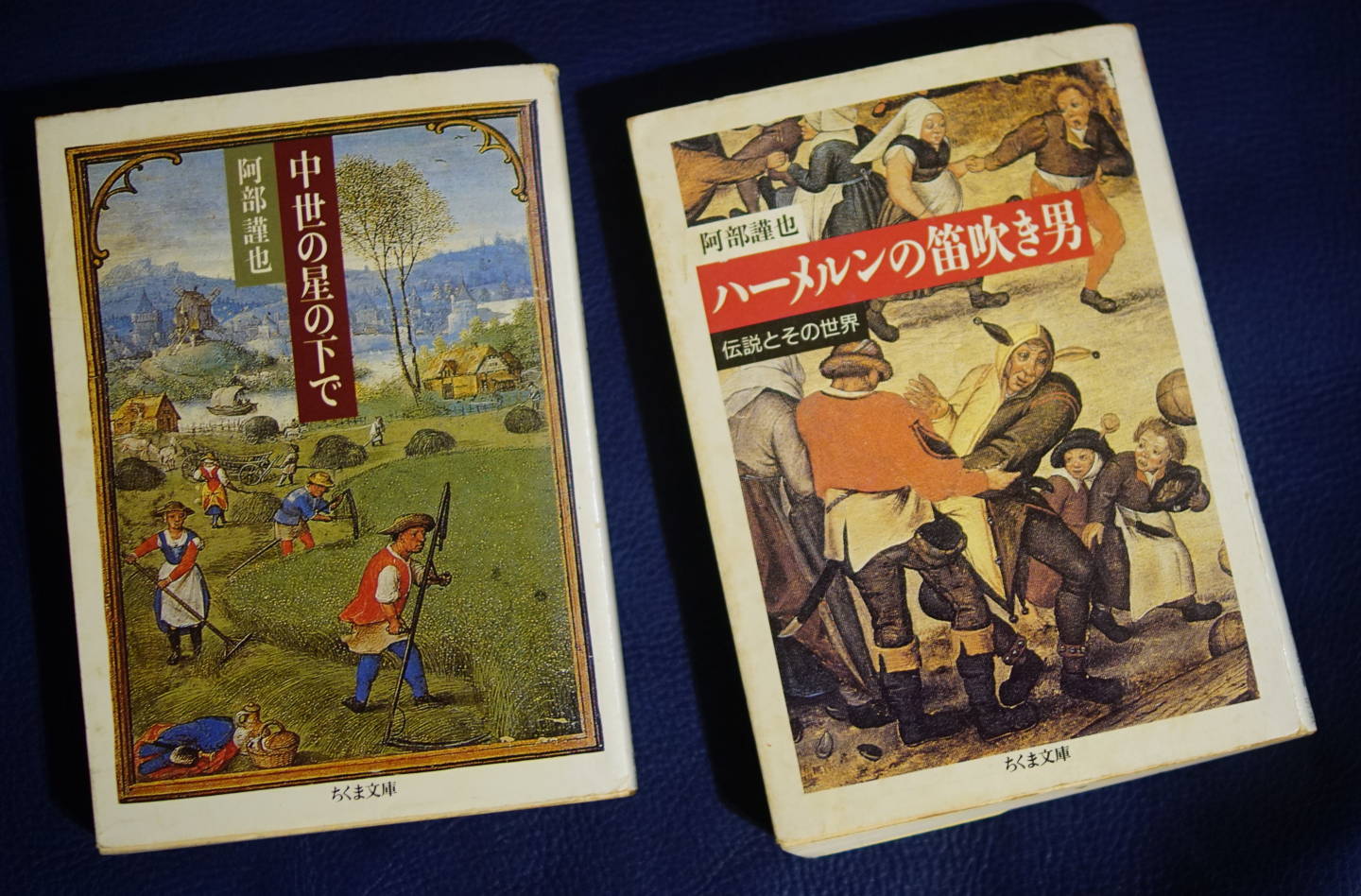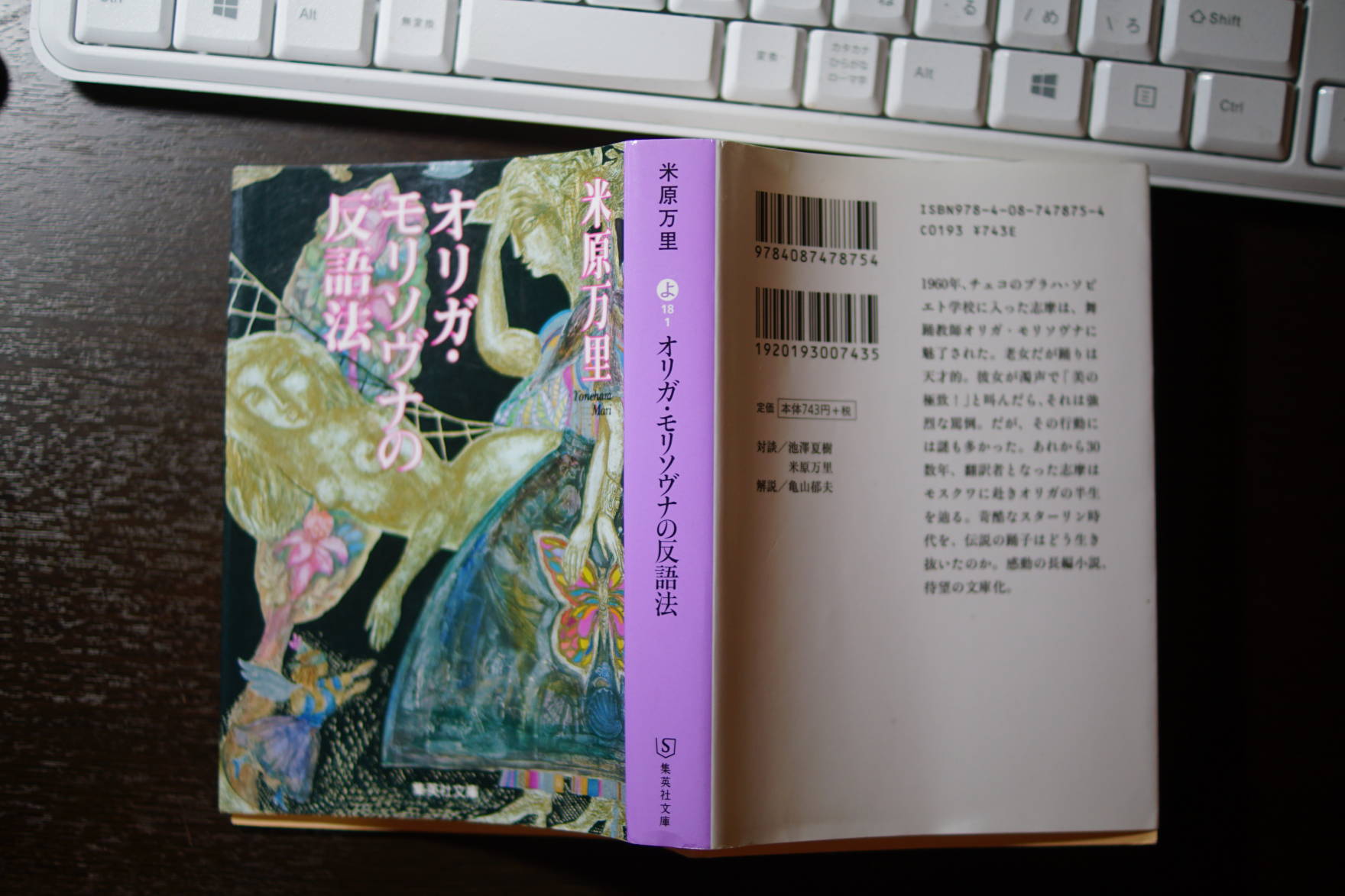小説のサブジャンルとして図書館ものというジャンルがある、という主張には同意していただけるかと思います。
『図書館戦争』というのは未読ですが、『図書館の魔女』は途中までは読みました。
外国の有名どころなら何と言っても『薔薇の名前』。
中島敦にも『文字禍』というのがありますね。
まあ、探せばいくらでも出てきます。
ノベリズムで連載中の『竜が居ない国』も、この範疇に入れて良いかもしれません。
例えばこのシーンとか
セヴィは廊下を更に奥へ奥へと進んで行った。廊下の左側の重厚な石壁にはところどころ、明り取りの窓が穿たれていたが、到底、人間が通れるようなものではない。右側の石壁には数字が刻まれた鉄の扉が並んでいる。
「どの扉の向こうにどんな書類が入っているのかも最高機密なんだ。俺も全部は知らないし、入れる部屋も制限されている。全ての部屋に入れるのは財務大臣と次官だけだ」
「財務大臣というのは貴族がなるものじゃなかったっけ」
「入れる権利はあるが、入れない」
「なんだそれ」
「ここまで来られるような時間の余裕を与えない。少しでも予定に隙間があれば陳情だの面会だの会議だのを秘書室が入れる」
「大変なもんだな、本当に」
「馬鹿馬鹿しいが、必要なことさ。さあ、ここだ。入ってくれ」
セヴィは鍵束を取り出して鉄扉の鍵をカチリと開け、まず自分が中に入り、ついでソルを招き入れた。部屋の中には天井まで届く巨大な書棚が数えきれないほど並んでいる。セヴィは反対側の窓際にある机の前まで行って、ソルを手招きした。
「俺の所属している局の書庫だよ。ま、座ってくれ」
ソルはセヴィが指さした木の椅子に腰を下ろした。背もたれがミシリと鳴った。
これは明確な元ネタがありまして。
これ。特に右のやつ。
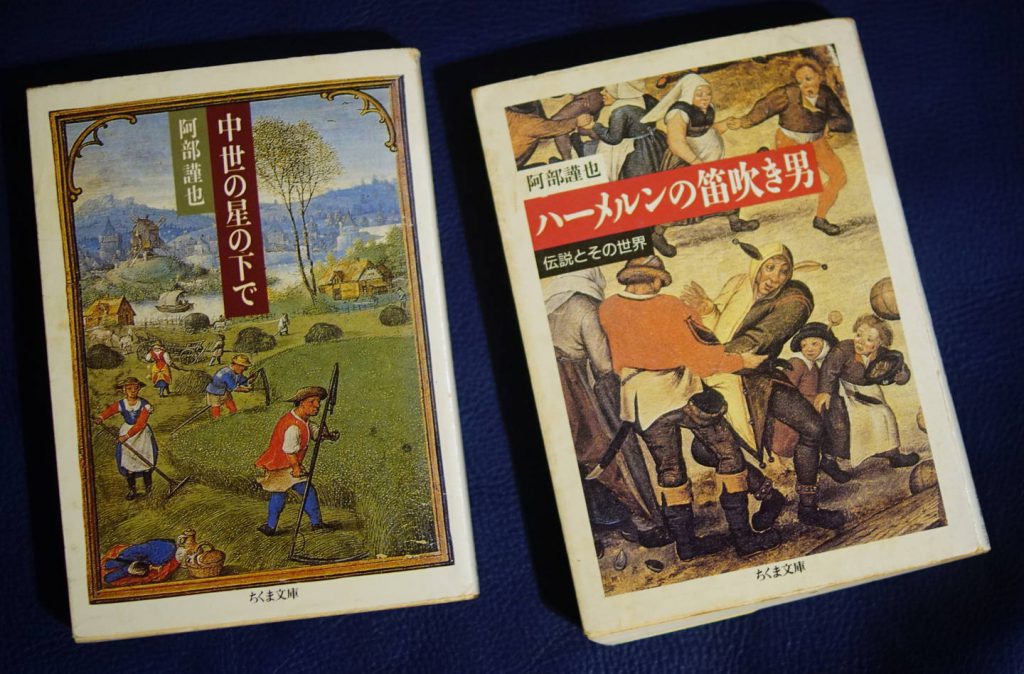
書き出しはこうです。
1971年5月のある日、私は西ドイツのゲッチンゲン市にある州立文書館の一室で14、5世紀の古文書、古写本の分析に没頭していた。古文書の分析それ自体はいわば単調な作業であって、精神の集中や高揚した気分を必要とはするが、古文書館の外で営まれている日常生活や世界の情勢、日本のニュースからは隔離された一種独特な雰囲気のなかで毎日営まれ、いわば世俗的な関心をいったん濾過した状態で進められるものである。
天井の高い静かな一室で、その日も私は一年半も毎日つづけられてきたのと同じような作業をつづけていた。私がその頃従事していたのは、バルト海に面した東プロイセンのある地域の古文書史料を徹底的に調査、分析する仕事なのだが、その日も例によってひとつの村の文書を系統的に調べていた。クルケン村の項を調べていた私はなんの気なしにこの村に関する最近の研究のページをくってみた。そのとき私の目にとびこんできたのが<鼠捕り男Rattenfänger >という言葉である。
阿部謹也さんが籠もっていたのはドイツ各地にあるStadtarchivという施設です。これは何かというと、ドイツという地域では中世から都市が発達していまして、詳しい説明はここでは端折りますが、市民による自治が行われていたのです。それに伴って、市民の誰がどんな権利を持っているのかを記録しておく必要が出てきます。この権利関係の資料を公的に保管していたのが、Stadtarchivです。建物の名前というよりは制度ですね。大聖堂の中に専用の棚を設けてそこに保管していたような時代もありました。
そんな文書の山を片っ端から読んでいた、という話は、阿部謹也さんの『歴史の中に自分を読む』に詳しく出ています。
まあ、そんなの面白いわけがないですよね。そのうちAIに読み取らせてAIにテキストデータ全部食わせて解析させるような時代になっていくんだと思いますが。
さて、私が研究者としてやっていたのも、阿部謹也さんと同じような、ロマンのかけらも無いような文献をひたすら読んでいって何かを見つけ出す、そういう作業です。
たまに面白いもの見つけたりしますよ。例えばハワイの航海カヌー文化復興の立役者ナイノア・トンプソンの海の師匠だったカワノ・ヨシオ氏のルーツを探した話とか。
1980年頃にヤップ島で何年もカヌーづくりをしていた日本人画家の手記の原本を国立民族学博物館のアーカイブに寄贈する仲介をしたこともあります。
でもまあほとんどは退屈です。
私が『竜が居ない国』の主人公にやらせるのは、そういう文献調査です。
何故そういうものを書こうとしたかというとですね、これまでの図書館ものって、図書館の描き方が過剰にロマンチックだったと思うんです。
もちろん図書館はロマンなんですが、「世界中の学者が血眼になって探し続けている幻の古文書」とか「魔法使いかと思えるような、何でも知っている超人的な司書」とか、本来の図書館の目指す方向と違う方向でロマン化されている気がしてならんのよ。
貴重書を所蔵していれば当然それは公表するし、然るべき手続きを踏めば誰でも閲覧出来るようにするものだし、文献資料の整理や検索は超人的司書の属人的なスキルではなくて図書分類法というシステムを使うべきだし、実際にそうなっています。ごく一部の幹部しか存在を知らない幻の蔵書とか、一子相伝で受け継がれる超人的司書のスキルとか、アホか。そういうのを反知性主義と呼ぶぞ。魔術や魔女の対極にあるのが図書館なんだよ。思想の向いてる方向が正反対なんだよ。ユネスコ公共図書館宣言を読め。
公共図書館は、その利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする、地域の情報センターである。
公共図書館のサービスは、年齢、人種、性別、宗教、国籍、言語、あるいは社会的身分を問わず、すべての人が平等に利用できるという原則に基づいて提供される。理由は何であれ、通常のサービスや資料の利用ができない人々、たとえば言語上の少数グループ(マイノリティ)、障害者、あるいは入院患者や受刑者に対しては、特別なサービスと資料が提供されなければならない。
いかなる年齢層の人々もその要求に応じた資料を見つけ出せなければならない。蔵書とサービスには、伝統的な資料とともに、あらゆる種類の適切なメディアと現代技術が含まれていなければならない。質の高い、地域の要求や状況に対応できるものであることが基本的要件である。資料には、人間の努力と想像の記憶とともに、現今の傾向や社会の進展が反映されていなければならない。
蔵書およびサービスは、いかなる種類の思想的、政治的、あるいは宗教的な検閲にも、また商業的な圧力にも屈してはならない。
大事なことはここに言い尽くされていると思います。誰に対しても平等に開かれていて、あらゆる知識や情報にスムーズにアクセス出来る。それが図書館のあるべき姿。選ばれた人しか入れないとか、変人の超人的司書に気に入られないと本を探せないとか、もう一度言う。アホか。
という思いがあり、『竜が居ない国』では、誰もがアクセス出来る公的記録の調査から主人公たちが謎に迫っていくというお話にしています。