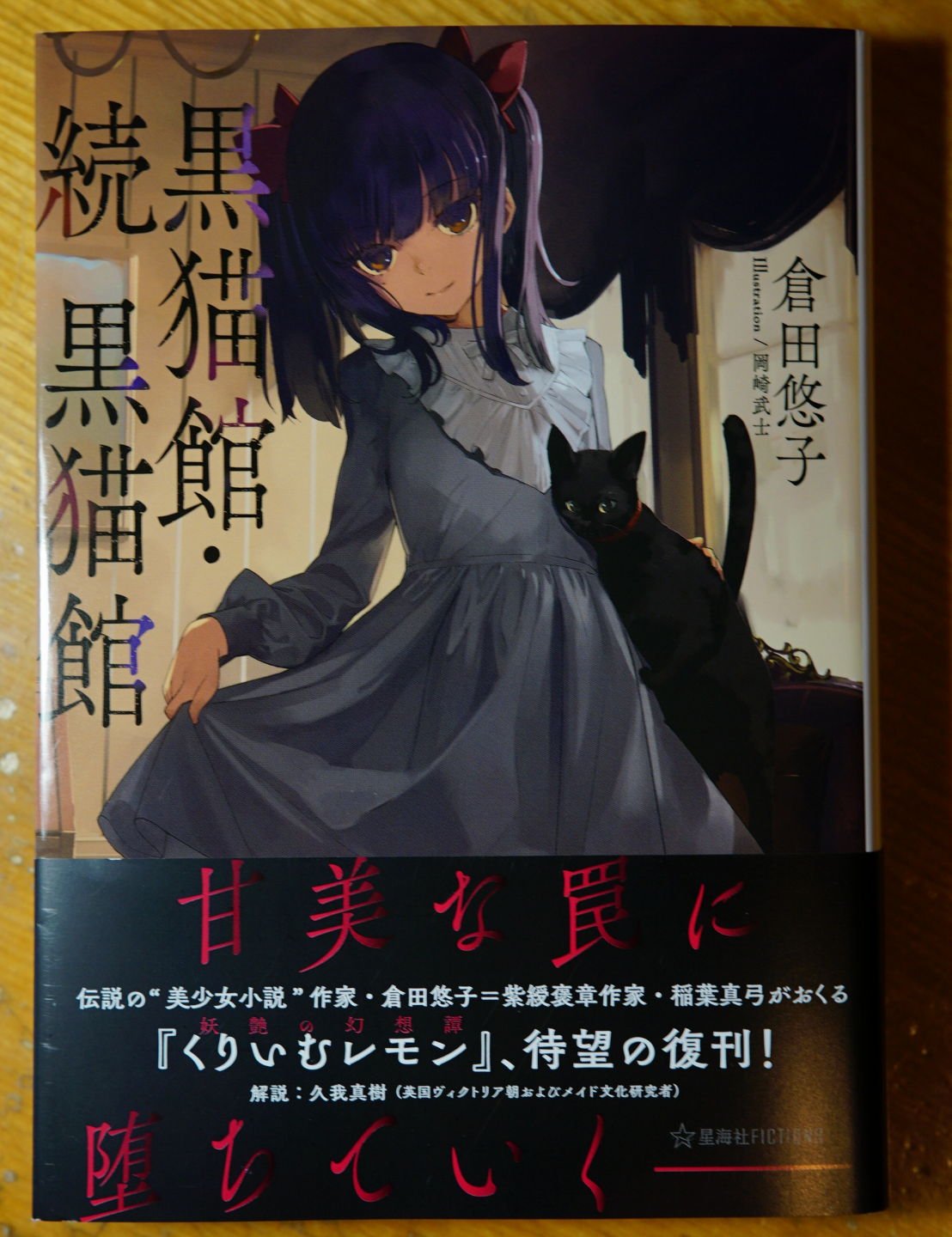一昨日は「阿波しらさぎ文学賞」の結果発表だったんだけど(注:私は不参加。その理由を説明するエントリである)、一次通過者とか最終審査まで上がった人とか、それなりに知り合いがいるのですよ。公募で上位に来る人ってある種の「常連」化するので、2年もコンスタントに公募レースに参加してれば自ずと知り合いって増えるわけです。
ただ、今回の「しらさぎ」を見ていて確信したことがあって、それはこれ。
「純文度が強いスリップストリーム文学(SFとファンタジーのこと)は市場が小さいわりに書き手供給過多なので、書籍や大手文芸誌デビュー済みのプロのキャリアラダーが無いに等しい。結果として、特に短編系の賞には本来ならもうこんなところは卒業していて然るべきプロがいつまでも参戦し続けるという地獄絵図」
今回の「しらさぎ」も、ハヤカワSF大賞取って長編デビューしてる十三不塔が一次通過者リストの中に名前があったし、こないだの創元SF短編賞の一次通過者の中には何と日本ファンタジーノベル大賞を勝っている大塚巳愛が居た。去年の「かぐやSFコンテスト」で優勝したのも2011年に日本ファンタジーノベル大賞を「さざなみの国」で取った勝山海百合。
大人気無いと思うなかれ。いや、大人気無いんだけどさ。
純文学系のファンタジーやSFの長編って市場がもんのすごく小さいから、ハヤカワや創元や新潮社の大きな賞を取っても次の弾をなかなか撃たせてもらえない。で、手頃なファンタジーやSFの短編賞にはその種のプロが大挙参戦し続ける。しかも短編の公募文学賞は主催者が出版社ではないケースが多いので、デビュー済みのプロが入り交じる激戦を勝ち抜いて1位になっても、賞金と賞品を渡されて終わり。長編単行本を出してプロデビューというステップに繋がらず、同じような短編公募を探しては投稿し続けることになる。
そういう構図がはっきり見えてしまっているので(むしろ皆さん見えてないのかが不思議)、こないだの「さなコン」でその種のスリップストリーム短編公募に手を出すのは最後にしようと考えた次第です。
あ、「さなコン」はさすがに受賞までは行かなかったですけど、最終に出られたので満足。私の本来の戦場はエンタメ一般文芸中長編公募なんで。コバルト短編小説新人賞である程度はライト文芸スタイルにも対応出来る手応えが出来たし、もともとハヤカワや創元が出すような日本人作家の作品ってそこまで趣味ど真ん中じゃないんですよ私。それよりはコバルトとか朝日ソノラマのが好きだったし、SFやファンタジー要素のあるものを絶対書きたいかというと、全然そうじゃないですから。
次はやはり氷室冴子青春文学賞か、文藝賞あたりもいいなあ。とにかくキャリアラダーが上につながってるやつね。専業作家になりたいわけじゃないんだけど、チャレンジするならやっぱずっと上の方に本屋大賞とか吉川英治文学新人賞とか直木賞とかあって、そこまでルートがつながってるものが良いです。グラスルーツ系の短編賞公募は腕試しや界隈内でのランク付け以上の意味は無いと思います。