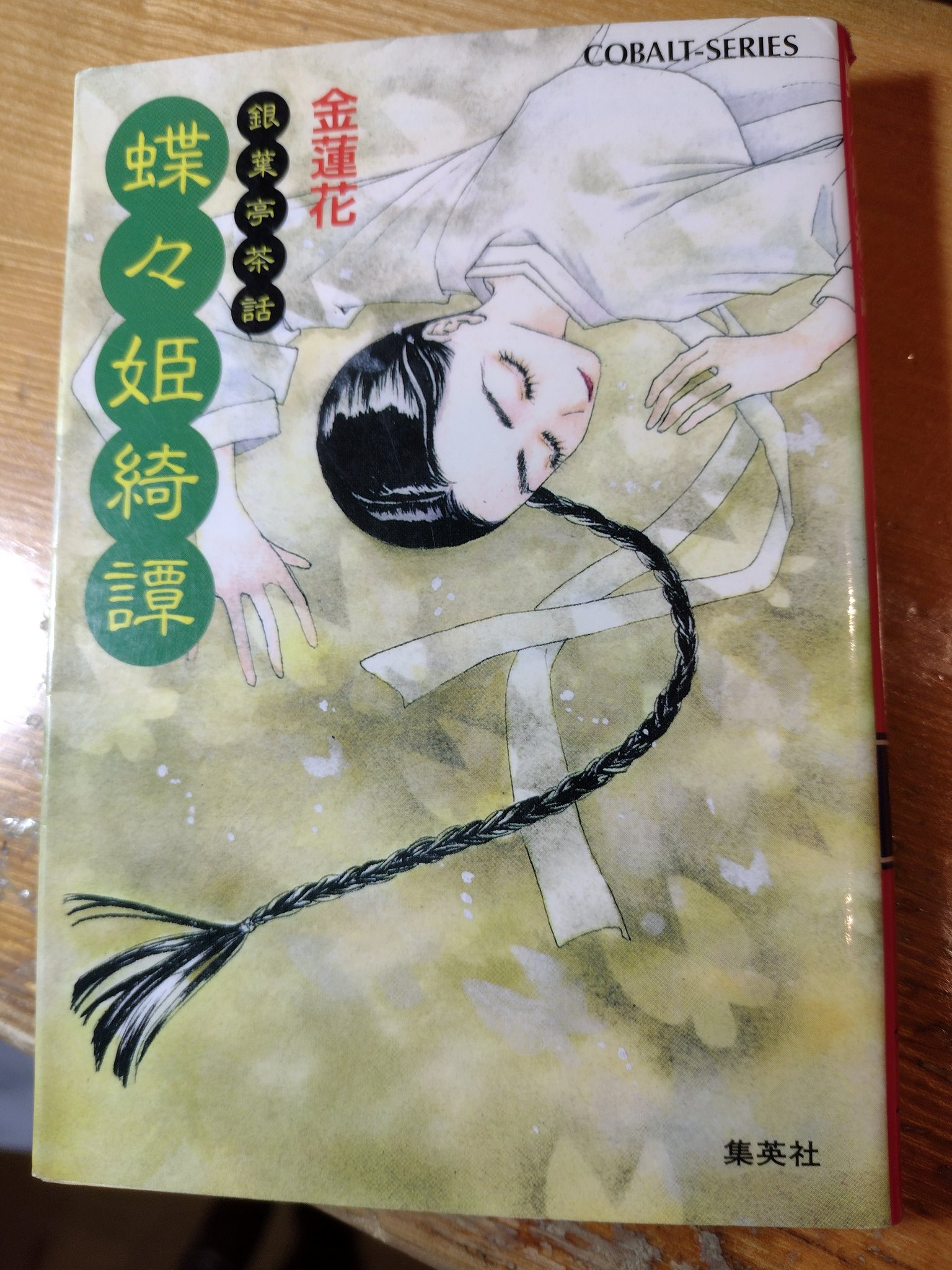高丘哲次『約束の果て:黒と紫の国』を読みました。
2019年の日本ファンタジーノベル大賞受賞作です。
最初に結論。これぞファンノベ大賞! という小説です。
今の日本でファンタジー小説というと、まずは「小説家になろう」系のものが想像されますね。それから少女小説の流れをくむ中華後宮ものラノベとか、あやかしコージーミステリー。そして上橋菜穂子や小野不由美、萩原規子といったビッグネームたちによる大長編ハイファンタジー。乾石智子もこの系譜の本格派です。
ですが、日本ファンタジーノベル大賞は、日本のファンタジー小説系の公募としては最も老舗で、なおかつ錚々たる大作家たちを輩出してきたブランドでありながら、実は上に挙げたような系統の作品は、知る限りでは1作品も大賞になっていない。
別稿でも指摘しましたが、ファンタジーノベル大賞を中世ヨーロッパ風異世界ファンタジーで取るというのは、凄まじく難易度が高いチャレンジだと思います。いや、そもそもド直球のハイファンタジーが勝ったことって無いんじゃないか? 日本ファンタジーノベル大賞を取るというチャレンジそのものが難易度AAAなのに、その中でも更に異常に難しい。あり得ないといっていいくらいにあり得ない。つまりは、そういうものを書く・書きたいなら電撃やファンタジアや講談社ライトノベルあたりを狙うべき、というような。そういうことです。
では、どういったものがこの文学賞で勝てるのか?
本作品はその一つの答え、というか、お手本というか、ベンチマークというか。
つまり、こういうことなんだよという作品。
それがどういうことなのかは、敢えてここでは書きません。まずは読もう。そして考えよう。これを読んでわからなければ、それはもう永遠にわからないですよ。
さて、小説の中身に戻ります。
序盤は伝説の第1回大賞『後宮小説』のオマージュとして始まります。構成的には枠物語です。枠物語として二つの小説が交互に出てきます。ですが、読んでいるうちにどんどん違和感が膨れ上がっていって、何かこれ変だろというところが、中盤以降で「そういうことだったのか」と謎解きされていく構造です。かなり大掛かりな叙述トリックが仕込んであります。枠物語の中に出てくる二つの「古文書」が近代小説みたいな文章になっている理由も、ちゃんと最後の方で伏線の1本として明かされます。テクニック的に、おおこれは上手いと唸らされた部分です。
ファンタジー要素に関しては、著者がゲンロンSFスクール出身ということもあるのか、ファンタジーの語彙で記述されたビッグブラザーものと言えるでしょうね。ビッグブラザーを中華ファンタジーの語彙に落とし込んで、更にもう2段階のメタファーを仕込んだ著者のひらめきは神がかっていると思います。これでファンノベ大賞取れなかったらおかしいだろうという仕込みがある。こういうのを学んで見習わないと、大賞までは手が届かないでしょう。
キャラ造形については、ヒロインが宮崎駿以降の日本のアニメの女子高生ヒロイン、あるいはセカイ系の女子高生ヒロインという造形なのが面白かったですね。ある種、ラノベ的とも言えます。オマージュの対象である『後宮小説』の銀河やセシャーミンはそんなでもなかったので、この辺は日本のファンタジー小説の発達史を考える上で注目すべきでしょう。念の為、良い悪いの話はしていませんよ。
あと、作中でヒロインと大きく絡む男の子キャラは二人いるんですが、ヒロインとの心理的距離や関係性が圧倒的に近くて深い方の男の子が最後、傍観者に回っていて、大スペクタクルのクライマックスからの泣かせるエピローグに続くストーリーラインが、もう一人の男の子との関係で作られていたのは、個人的には「え? そっちの子だったの?」という驚きはありました。
また、ラストバトルはナウシカ~もののけ姫~エヴァンゲリオンという、これも日本のSF/ファンタジーアニメのど真ん中へのオマージュを目一杯ぶち込んだ超スケールのもので、あれ、サイズ的には超銀河グレンラガンとかエヴァ旧劇場版の最後らへんに出てくる綾波くらいのやつですよね。すげえぜ。アクセル踏み抜いてる。
|
|
というわけで、とにかく読みましょうみなさん。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0a0ae637.10e48172.0a0ae638.5577ea7e/?me_id=1213310&item_id=19939373&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2118%2F9784103532118.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)