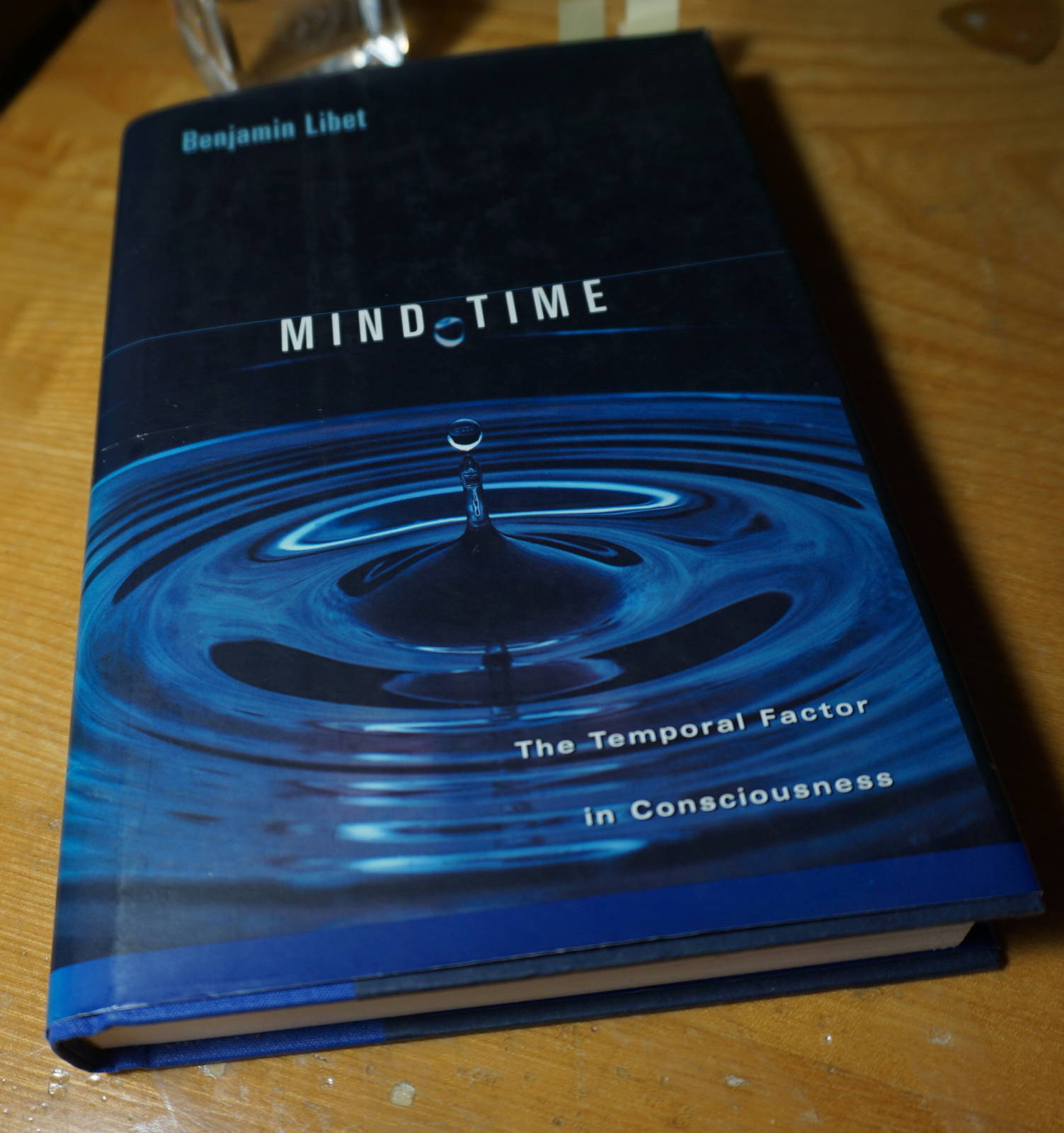4年前の日本ファンタジーノベル大賞受賞作『隣のずこずこ』を(飛ばし読みだけれど)読みました。
小説自体は、面白かったです。これ書いた人は当時は学生で、なんていうんでしょう、いつの時代にも20歳前後の若者のある部分に存在する虚無感や無力感を、上手く信楽焼のタヌキと結びつけたなと。
もちろん私も今やいい年なんで、「あー、その年頃だとそういう感覚持ったりしますよね。あったあった」という形での受容になります。
面白かったというのは、虚無感を信楽焼のタヌキというビジュアルにくっつけた意外性。その手があったか! やるじゃん。すげえぜ。という。
さて、この狸型の破壊神の設定は以下の通りです。
1) 狸型の破壊神は集落を毎月一つ、その月の最終日に完全破壊し、住民を全て抹殺する。
2) 破壊された集落と抹殺された住民の記憶は、破壊神のナビゲータ役を強制アサインされた1人の人間以外はこの世界から消滅する。
3) ナビゲータ役を殺した人は次のナビゲータ役になる。
4) 設定1は当地方の住民なら皆知っている。
YES。
ロジックが2箇所で破綻しています。
破綻箇所A:設定1) が真なら 4) は偽となります。逆も同じ。
破綻箇所B:毎月1箇所ずつ集落を完全消滅させていったら、1年で12箇所。3年なら36箇所。10年で120箇所。そのペースで集落を消していたら、あっという間に当地方から集落は無くなってしまう。
また、信楽焼のたぬきは1931年にデザインされたものなので、昔話に出てくるとしたらそれは捏造あるいは変形された昔話です。
|
|
さて、こういった設定破綻をどう評価するか。
もちろん「そんなことはどうでも良いんだよ」が基本です。この小説は不条理を表現したいのだから、設定が不条理であることは織り込み済み。
「進撃の巨人」だって「鬼滅の刃」だって、そんなことを気にしていたら読めません。不条理がテーマなんだから設定は破綻していたってOK。それが大人の余裕で子供の純真。
でも私は気にしちゃうんだな。
あれ、ここおかしくないか? ロジックが壊れているだろ。
はい、終了。そこから先は飛ばし読みで一応ラストシーンだけ確認して、なるほどそういうオチなのかと理解して、次の本へ。
自分でも変なこだわりだと思います。だから不条理SFや不条理ファンタジーとの相性が極端に悪い。不条理時代劇とか。「そんなことしてたらあっという間に公権力に取り締まられてゲームオーバーじゃないですか?」みたいな荒唐無稽な設定の時代劇、ありますよね。
多少の設定の粗はあっても、物語のテーマが不条理の表現ではない作品であれば、気にならないんです。熱血とか熱愛とか正義とかそういうことを語りたいんなら、良いの。
でも、不条理を表現したい作品で
「あれ? ここ設定壊れてるじゃん? かんたんにハック出来るじゃん? というかこれゲームがバグって最初から動かなくない?」
というものが見えると、
「デバッグしてから出してくれ」
と思う。
いやまあそうは言っても、熱血の演出に不条理を使ってる場合、「そんなに頑張らなくてもこの敵はここバグってるから、アタマ使ってハックしたら簡単に倒せるでしょ」とか思うわけですが。
あー性格悪い。
追記:この性格の悪さは息子にも受け継がれているようで、「ねえ父ちゃん、鬼殺隊は何でヴィッカース重機関銃に藤の花から抽出した薬品を塗布して鬼を虐殺しないの? 大正時代ならヴィッカースMk.1あるよね?」と質問されました。「産屋敷耀哉は1000年に1人出るか出ないかクラスのバカだからだろう」と答えておきましたが・・・・


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0a0ae637.10e48172.0a0ae638.5577ea7e/?me_id=1213310&item_id=20177787&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4417%2F9784101024417.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)