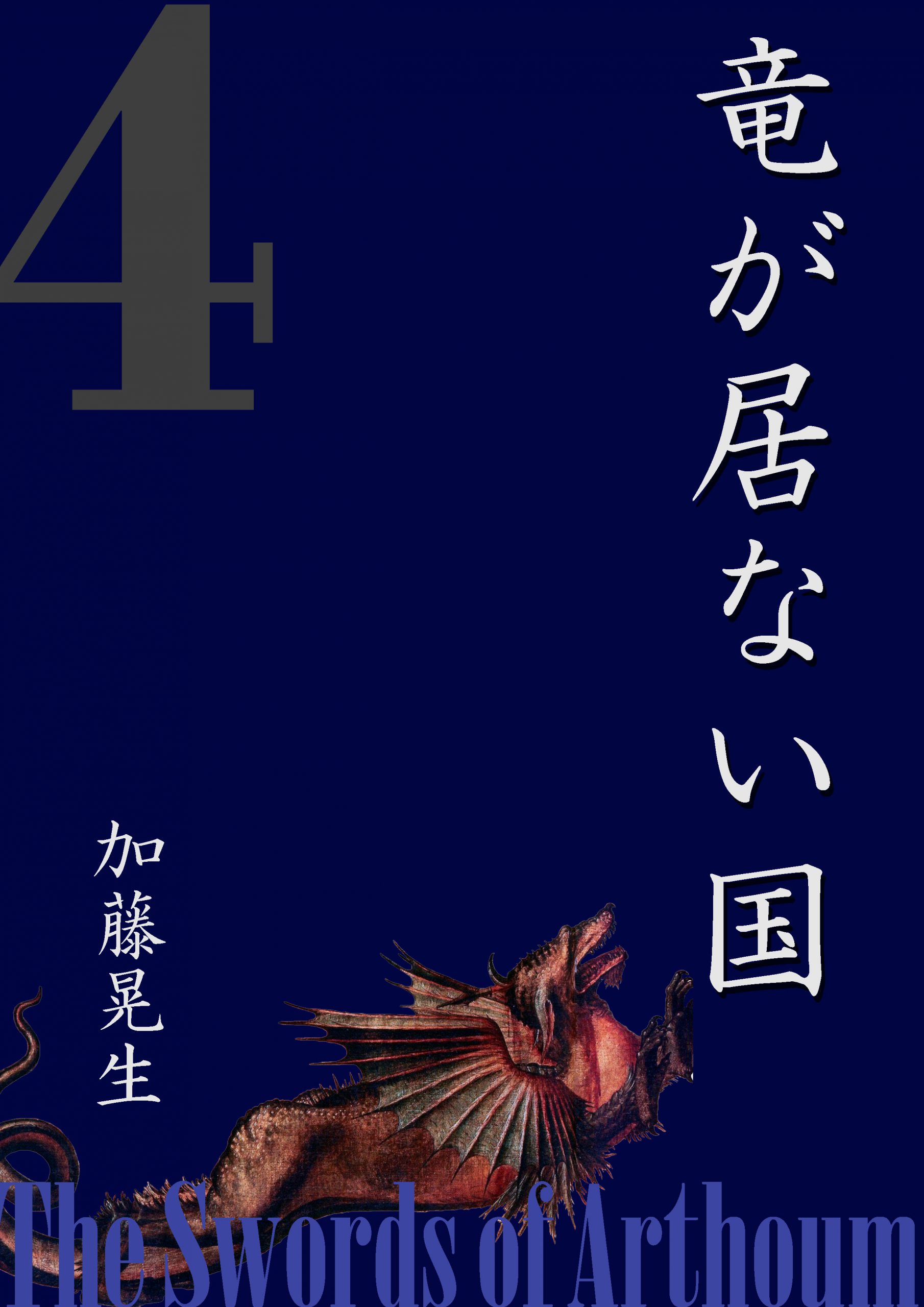今年になって自分がずっと書き続けている異世界小説には「傭兵組合」というものが登場する。
作中の時系列で2作目になる「竜の居ない国」ではかなり重要な役割を担い、3作目「叙任式」ではこの組織そのものが舞台となった。
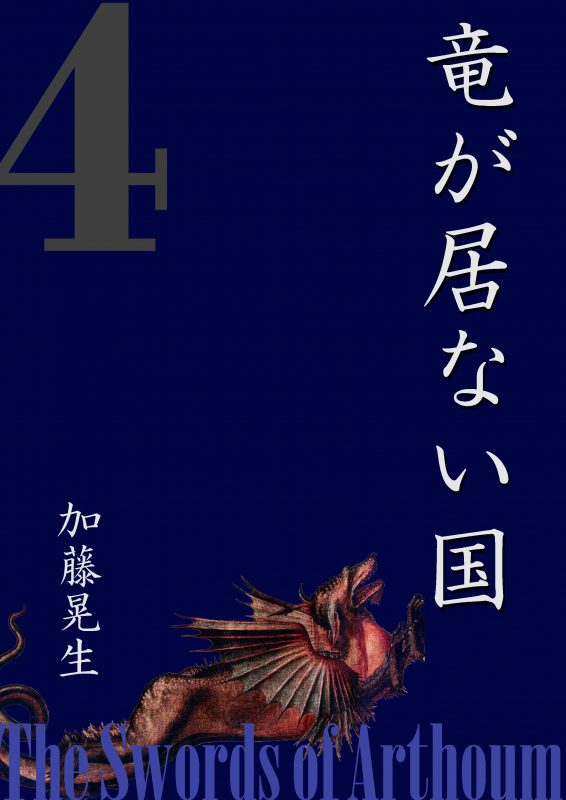
竜が居ない国
一見すると、ナーロッパによくある「冒険者ギルド」に似た組織のようにも見えるが、実際にはかなり違うタイプの組織である。
「冒険者ギルド」は管見の限りでは中世ヨーロッパの商業ギルドや手工業者ギルドとも全く異なる得体の知れない国際組織のようだが、拙作に登場する「傭兵組合」はアルソウム連合王国の国主(「六つの冠の主」)から与えられた勅許状によって設立を認められた全国組織だ。
その特徴は「国家に認可された全国組織であり、特定の職種の品質認証・保証を独占的・排他的に実施している」となる(現代日本なら公益財団法人や社団法人で似たようなものが色々ある)。
ちなみに中世ヨーロッパのギルド/ツンフトは都市単位で結成されており、都市の自治の枠の中で活動しており、それ故に君主の勅許を必要としない(知る限りでは。ただしロンドン市の諸ギルドなど勅許状を取得しているギルドも無いわけではない)。
だから、権力構造から見ると以下のような違いとなる
【中世ヨーロッパのギルド】
国家権力>都市>ギルド
【拙作における勅許同業者組合】
国家権力>組合
ここまでが権力構造から見た「傭兵組合」の位置づけである。
何故こうした組合を登場させようと思ったのか。
実際のところ、成り行きである。
最初に書いた「竜の居ない国」で物理的暴力(からの防御)を担当するキャラを出す必要があったのだが、立場的には彼は国家権力サイドであり、なおかつ公務員ではなく謎の戦士である必要があった。というのは、主人公が一時的にせよ国家公務員として動くことになるので、そのチームメイトを兵士や警官にしてしまうと、話が(「兵站貴族」で扱っているような)公務員組織のタテ割り問題に寄ってきてしまうのである。「竜の居ない国」のプロットは私のようなフリーランスのコンサルタントが巨大公共事業のチェンジ・マネジメントのための予備調査を行うというものなので、主人公チームはフリーランスのコンサルタントで固めたかった。
そこで考えたのが、国家から戦士が品質認証を受ける制度である。更に彼に若い子分を同行させたかったので、その関係性を中世ヨーロッパの徒弟制を流用して定義した。つまり、中世ヨーロッパに存在した権力制度のうち、君主から直接与えられる特許であるRoyal Charterと、都市自治の中で発展したapprenticeshipをくっつけたのだ。
更に6人の実働チームの属性を以下のように設定した。

この各キャラクターセットには、もちろんここには書かれていない隠し変数が色々あって、キャラクターたちの行動を複雑にしている。あまり詳しく仕掛けを説明すると読む楽しみを奪うので、何故、この3セットを組んだのかは各自がいずれ考察されたい。ヒントを書いておくと、Royal Charterとapprenticeshipという対比は、この作品を西洋古典音楽に喩えるならば、その主題労作の表現の一つである(主題そのものではない)。
さて、たまたま思いついたこの「傭兵組合」という仕組みは予想外に上手く作品世界にハマってくれた。
常備軍というのは拙作の作中でも金食い虫である。例えば2000人の兵士で構成される部隊の年間人件費は金貨108000枚としている。作中の金貨は現代日本の通貨でおよそ8-10万円として様々なものの価格を決めているが、仮に8万円で計算しても86億4000万円だ。アルソウム連合王国は世界有数の大国という設定であるが、それでも常備軍を10万人も雇っておけるほどの財力は、どう考えても持たせられない。
そこで考えたのが、平時は下士官含めた兵士の半分は解雇してしまい、いざという時だけ呼び集めるシステムである。
これに必要となるのが、解雇して野に放った兵士たちが野盗に化けない、そして再徴募の際に確実に彼らにリーチ出来る仕組みだ。
「傭兵組合」はこれにぴったりである。従軍経験によって親方資格を得ることが出来て、平時は各種の警備の仕事を独占的に専門職として斡旋してもらうことが出来る。また勅許状を剥奪されないためには組合は自治に注力し、組合員が法を犯さないように取り締まらなければならない。
そして戦時となれば同じ組織が全国の部隊に彼らを古参兵として速やかに送り込む。
平時編成の連隊に残った兵士たちはジャンダルムリ(国家憲兵。警察業務を行う軍人のこと)や土建屋として活動させることで、人件費の浪費を回避する。
おお、なんか、行ける気がする!
かくして、「冒険者ギルド」ではない形で戦士の自治組織を近世社会に実装することが出来たのでした。