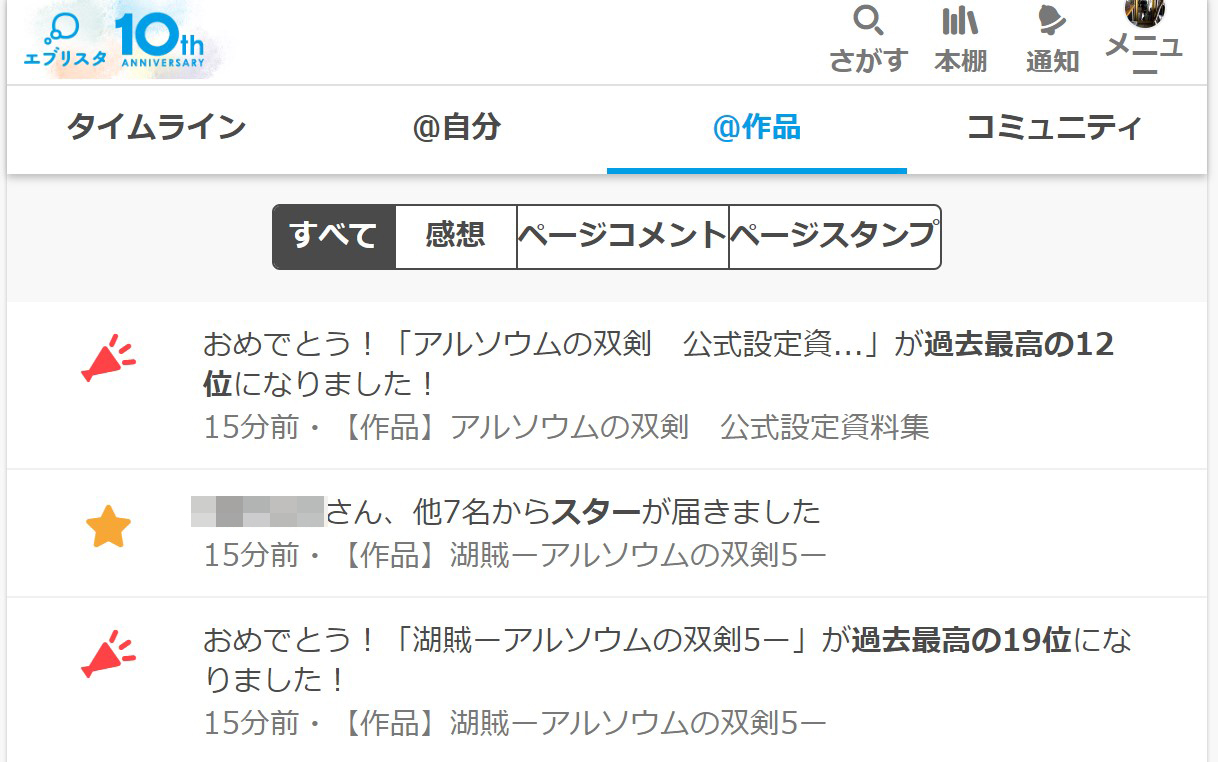仮面ライダーゼロワンの最終回に対する反応(の一部)を見ていて面白いなあと思ったことを以下に列挙する
1) 自分の好みじゃない展開・演出だからダメな作品と断定する人がいる
→個人的な好き嫌いと客観的な品質の区別が出来ない人。意外に多い。
2) 「充分な機械学習が時にシンギュラリティに到達する」という作品の基礎設定を理解出来ていない人がいる
→高性能なAIを搭載されたロボットが工場出荷後の初回起動時から自我や個性を持っているという「ドラえもん」「鉄腕アトム」的な設定とヒューマギアの違いを認識しないまま後期思春期的な問題意識で二代目イズと主人公の関係性について違和感を表明している人。驚くほど多い。
3) 多様な解釈の余地がある演出を受け入れられない人がいる。
→あらゆる伏線やエピソードに対して明確な(自分好みの)決着が作品内で語られていないと、「モヤモヤする」人。いっぱいいた。
つまり「主観と客観の区別が出来ない」「取説を読まない・他人の話をきちんと聞かない」「徹底的にわかりやすくなっていないものに耐えられない」という・・・・特撮への不満だけで済めばいいんだけど、きっと別の場所でも・・・・・おっと。
そう言えば、アーシュラ・K・ル=グウィンのエッセイで「眠り姫」について書かれたものの中に、面白い一節があった。
「わたしたちはあのお伽話をわかりやすくすることができる。汚すことができる。話の倫理性が高まるように語り直すことができる。「メッセージ」を伝えるために利用することもできる。わたしたちがそういうことをしたあとも、あのお伽話は依然としてそこにある。茨垣の内側の場所に。その静けさ。そこに降り注ぐ日の光。眠っている人々。何ひとつ変化しない場所。母さんたちと父さんたちは子どもたちにあのお伽話を読み聞かせ、それは子どもたちに影響を及ぼすだろう。
あの物語自体がまじないなのだ。誰がそれを解きたいと思うだろう」(『いまファンタジーにできること』河出書房新社2011年、28ページ)
充分に知的な人物であれば、この一節を「仮面ライダーゼロワン」に当てはめたときに何が見えてくるかを想像することが出来るだろう。