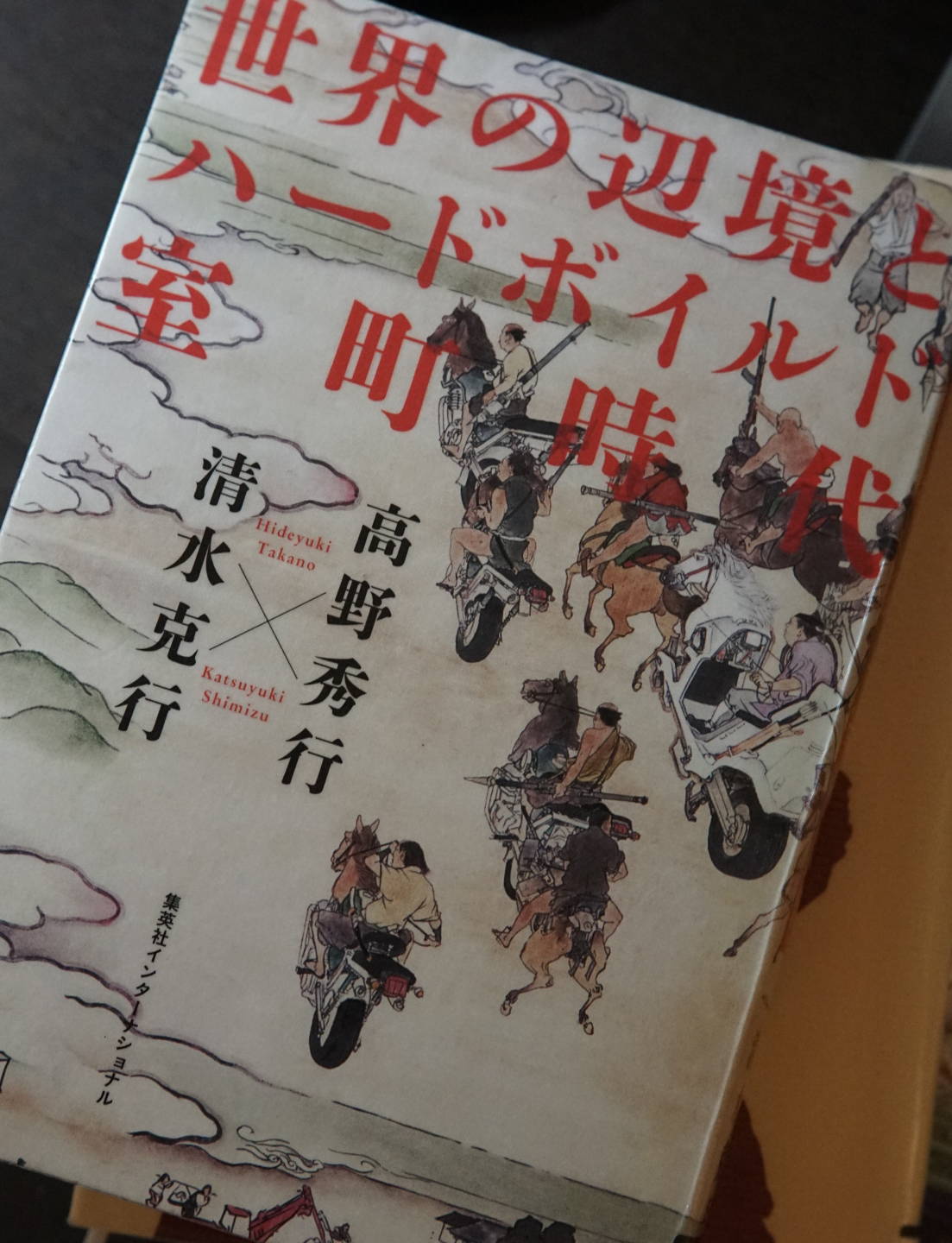高田大介『図書館の魔女』を下巻まで読んだ。
軍事関係の設定は荒唐無稽の極みに思える。第二次大戦の東部戦線のイメージで13世紀ヨーロッパの重装騎兵偏重戦術を描いているような。
軍船に火砲が搭載されているのに野戦に砲兵が出ないとか(三兵戦術についての記述、無いですよね)。
20世紀後半レベルの学術知識を自在に動員できる一ノ谷軍に戦列歩兵はいないのだろうか? マスケット銃兵は? 古代に水撃ポンプが発明されているような町なのに。
また軍師キリン女史がナポレオンの(画餅に帰した)補給部隊構想みたいなものを披露しているのだが、膨大な常備軍が前線に張り付き、後方から補給部隊が梯団を組んで物資を届けられるようになったのは、産業革命が起きて鉄道と自動車が兵站に使えるようになった20世紀以降、しかもそれらのオペレーションがまともになるのは第二次大戦終盤の連合国軍において、ようやくのこと。
キリン女史は重装騎兵の大集団が迅速に移動して内線作戦を展開するというような理論を展開しているが、その重装騎兵1人を行軍させるためには5人以上の兵站スタッフが随行しなければならない。そして巨大な軍馬を稼働させるには莫大な飼い葉を供給し続けなければならない。これらの兵站スタッフは徒歩移動になるから、1日あたりの行軍距離は15kmから20kmも行ければ上等だ。また街道の容量を超えれば渋滞が発生し、更に行軍速度は遅れる。交通集中による渋滞発生を兵站が回避できるようになったのはDデイ後のこと(しかも行きと帰りで専用の道を指定するという力技)。
いくらトップの参謀が優秀でチートでも現場スタッフは違うのだ。現代においてすら、数学を駆使した高度な物流改善コンサルのプランは、現場ではなかなか実装出来ない。理屈と現実が違うというのは、やってみないと見落としがあるという他にも、膨大な現場スタッフに従来の仕組みをアンラーニングさせて再教育する凄まじいスイッチングコストが発生するというのが大きいのだ。ことの半分は現場の「お気持ち」の問題で、8割は失敗するくらいの覚悟が必要だ。
ただし、そういった部分をいちいち描いていたら夢も希望も無くなって面白くないので、天才軍師の天才的発想で問題が一気に解決というストーリーテリングのカタルシスを持ってくるのが、ファンタジーエンタメとしては絶対に正しいです。