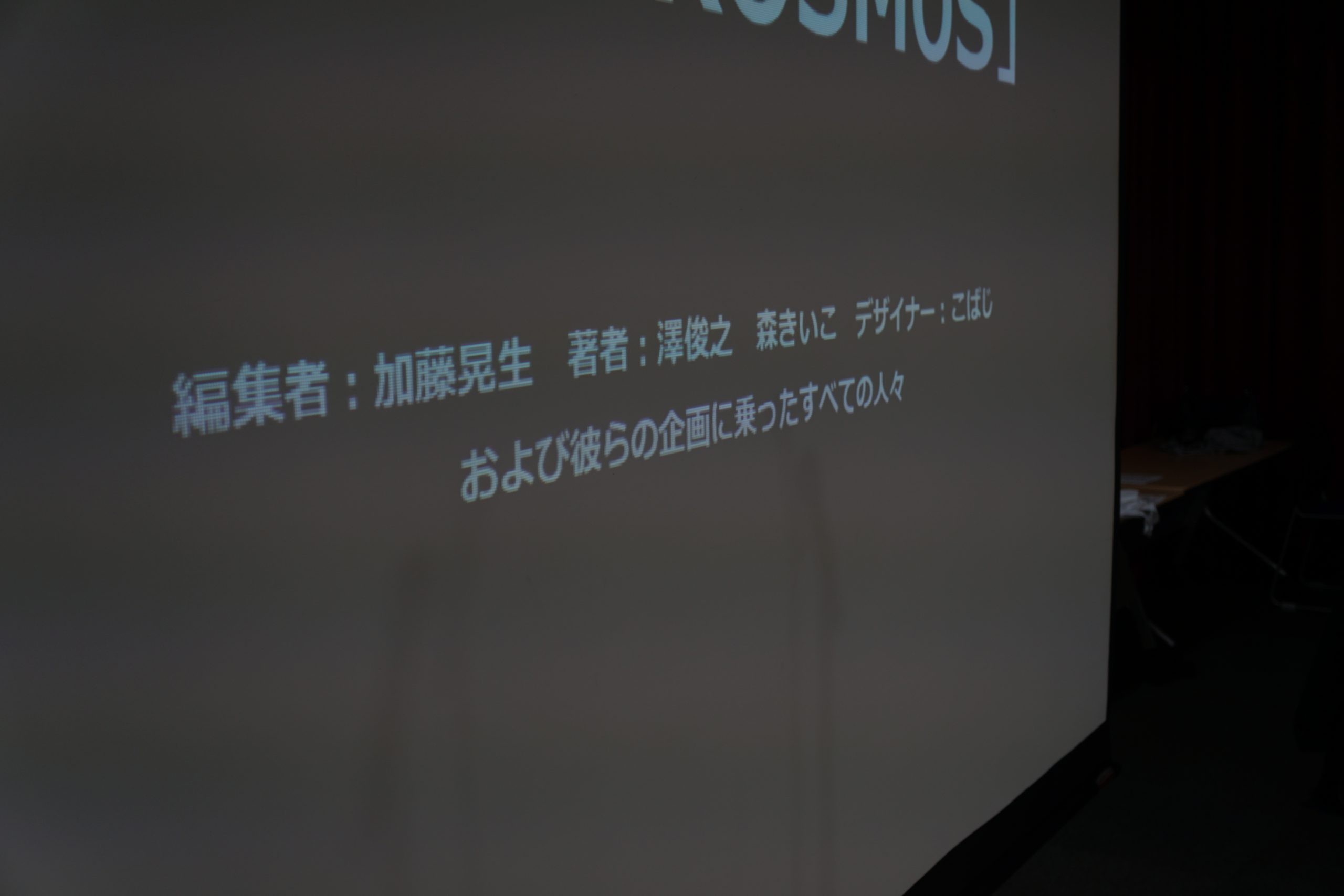2ヶ月ほど宿題っぽく残している企画書がある。
新しいサービスの企画を考えようということなんだけれど、何かこう、芯が一本ビシッと通らない感じがあって躊躇っていた。
何がそう感じさせていたのか。ようやく昨日と今日でわかってきたような気がする。
一言で言えば、エンドユーザーが本当にもとめているものは何かということ。最初に「こんな感じで」という大雑把な枠組みの提示があったのだけれども、それはあくまでもサービスプロバイダの視点からの視界だった。
それを、エンドユーザーの視点からの視界に置き換えて、手前から地平線の先まで要素をスラッと整理整列させてみたら良いのではないか。
そんな気がしたのは、NovelJamのKOSMOSの活動に昨晩、句読点を打った瞬間だ。
我々は販促キャンペーンの最後に、KOSMOSの4人以外で一緒に「天籟日記」や「we’re Men’s dream」の世界を作ってくれた人たちへの感謝を表明した。

そうした理由は、まずなによりも「一緒に盛り上げてくれてありがとう」と心からお伝えしたいからなのだ。
「買ってくれてありがとう」
「読んでくれてありがとう」
ではない。
もちろん、それも本当にありがたいのだけれど、それはこちらの都合でしかない。買って欲しかったのは我々だ。読んで欲しかったのも我々だ。
昨晩、一人ひとりのお名前を書き、メッセージを考えている時に考えたのは「買う」「読む」より奥に、先にあったはずの何が、この人たちを動かしたのだろうかということ。
あそこに名前が並んだ人たちが「買うこと」「読むこと」によって手に入れたものは何だったのだろうか。
しかし、それこそがKOSMOSが作って、渡したものの本体である。文章や絵はその写し身でしかない。プラトンならば、善とか光と言ったはずの、作品の向こう側にあって作品を輝かせているなにか。光源。そこが「天籟」や「メンドリ」の価値の存在する座標だ。
何かを売るのであれば、モノやサービスだけ見るのではなく、それを手にすることで消費者は実際には何を手に入れようとしているのか、手に入れているのか。そこを考えなくてはいけない。
それは、やはり、消費者と真剣にコミュニケートしなければ感じられない。見えてこない。
NovelJamという不思議な試みに関わってみて得られた一つの教訓は、当たり前すぎるくらい当たり前のお話の再話だった。
KOSMOSのキャラクター小説群が運んだのは、「書く/描く」ことに向かって一歩を踏み出す勢いそのものだった、ような気がしている。