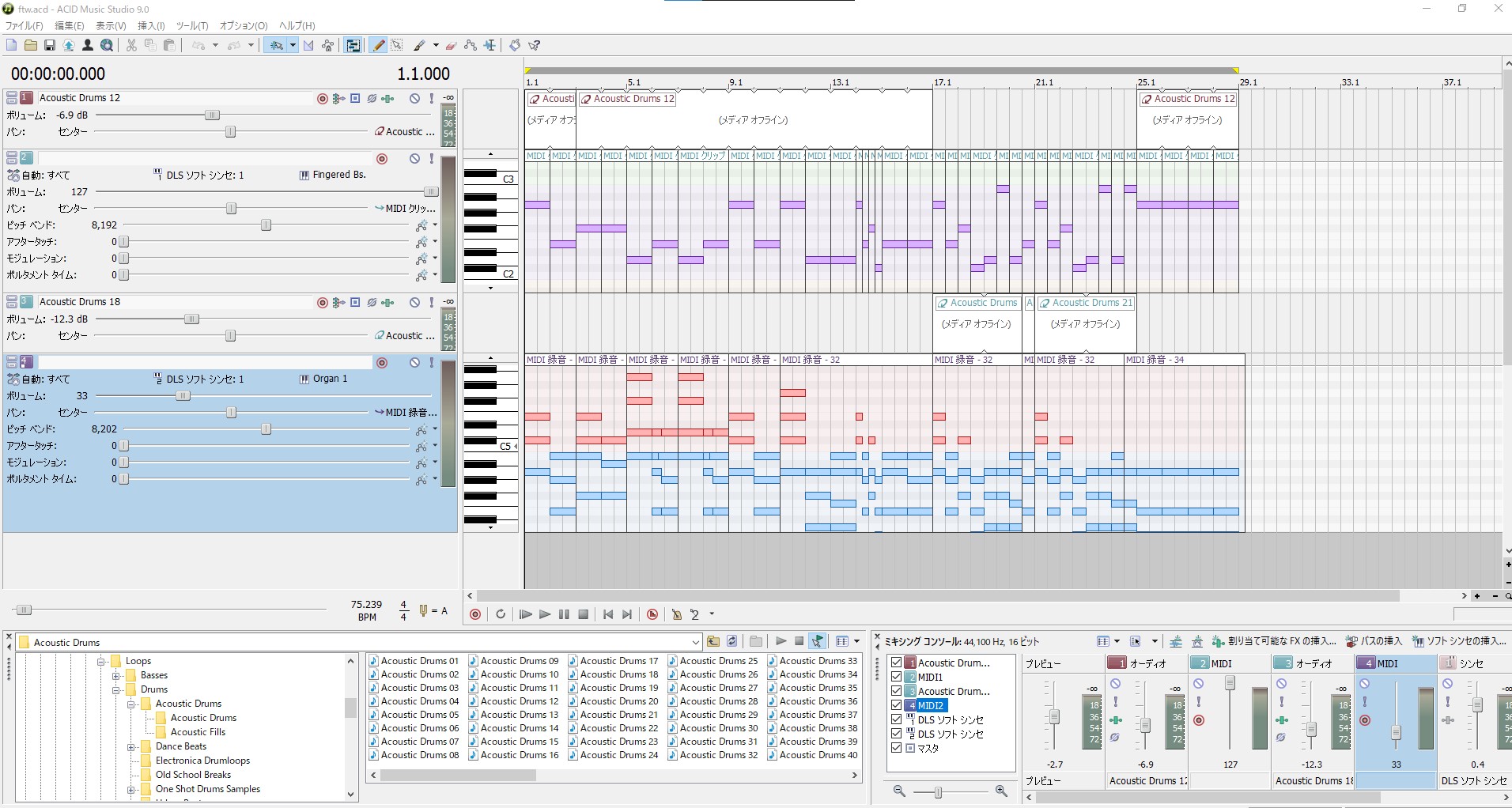こちらのセイタロウデザインさんでの連載、いよいよ本編に入りまして、もう手加減無しのアカデミック・ライティングでセイタロウデザインのブランディングパートナー事業の分析を進めています。
方法としては、セイタロウデザインのクライアントの一つであるA社のブランディングプロセスを順を追って記録し、私と山崎晴太郎さんそれぞれが分析・考察を加えるという形になっています。
一般的な学術書や論文ですと、分析・考察は調査をしている者(この場合は、私)だけが行うのですが、今回は基本となるコンセプトが
「山崎晴太郎の思考の客観的な言語化と理論化を、山崎晴太郎自身が試みる」
というものなので、考察部分では観察される対象である山崎晴太郎さん自身も長文の分析を行っています。
いわゆる「自己分析」というやつですね。
よくキャリア関係の分野で行なわれるものに似ていますが、この連載では「自己分析」の前段階でガチガチにアカデミックで客観的な記述を入れているところが面白いと思います。
私の性格もありまして、このパートでは山崎晴太郎さんに対する忖度はゼロです。
ゼロ。
手加減無し。容赦無し。持ち上げるつもりは一切無し。
だから、原稿を晴太郎さんに回す前には結構勇気出してますよ。
私もちっこい商売とはいえ、企業のコンサルティングをやっているわけですが、あのですね、レポートで手加減無しで「御社のここがアレです」って書いたり言ったりすると、怒っちゃう人は怒っちゃうんです。で、あとから
「所詮は学者先生だから、現場のことなんかわからないんですよね、って○○さんが言ってました」
という噂だけ伝わってくるの。
ですが、ありがたいことに晴太郎さんはその辺は全く気にされないので、私の心筋はいい感じのインターバルトレーニングをさせていただいております。ありがたいです。
さて、そんな異常な連載ですが、もちろん楽しくて読みやすいウェブ記事やコンサル本に慣れた方々には大層読みづらいことは承知の上で、以下のような「他にはない特徴」があると思っています。
1) ブランディングのプロセスが克明に記録されていきます
この連載のための調査としてブランディング本は山ほど読みましたが、どれも肝心要のところはモザイクがかかってるんですよ。
そりゃあ、それぞれのデザインファームの飯の種ですから、考え方は本にして売ったとしても、具体的な手順は書けません。
しかしですね。恐ろしいことに、私は今回、A社関連の全ての情報へのアクセス権を貰っちゃってます。
ここにあるものはどれでも自由に見て分析してくださいと。
で、忖度無しで記録していくわけですから、A社がどの会社かということが特定出来る情報以外は、ありのままのセイタロウデザインの仕事の手順が表に出てきます。
このレベルのデザインファームで、そんな解像度で仕事の中身を晒すって前代未聞ですよ。
2) 山崎晴太郎の思想・思考が学術書レベルの精度と解像度で言語化されていきます
今回アップされたものの次、後編というパートでいきなりめちゃくちゃな長文で出てきますが、はい、随筆レベルではなくて大学院の教科書に使えるくらいの厳密さ、精密さで晴太郎さんの考えていることが文章になっています。
以前にアップしたものも、読んだデザイナーさんが「1度読んだだけでは理解出来なかった」「もう7回読み返した」とおっしゃっていると聞きましたが、たぶん、この連載を1度読んだだけで理解出来るのは最低でも修士号を持っているような人だと思います。
でも、何度も読み返せばかなり多くの人に理解出来るような書き方も心がけています。
私が大学院生だった時、とあるネット掲示板でこんなようなことを言われたんですよ。
「簡単なことを難しく書いているだけの文章と、本質的に複雑なことを、複雑さを損なわずに出来る限り簡単に書いた文章は違う」
たぶん、ポストモダンやカルスタ界隈で量産されていた「簡単なことを難しく書いているだけの文章」への批判だったと思うのですが、あれからかれこれ20年。ずっとこの言葉はこころに残っていました。
簡単なことを難しく書くのは、慣れれば出来ます。難しいことを簡単に噛み砕いて書ける人も多いです。
でも、前者は余計なノイズを大量に付加しているだけですし、後者は本当は大事な情報を削ぎ落とすことで読みやすくしているだけです。
ハイレゾ音源とmp3の違いみたいなものです。
今回、私たちが挑戦しているのは「それなりに複雑な構造を持っていて、一言では絶対に言い表せないものを、その複雑な構造のトポロジーを一切壊さないまま、可能な限りシンプルでスムーズな言葉で記述する」ということです。
大事なことを一つも捨てないということを大原則として、全力で読みやすく文章にする。
その結果がやはりとっつきにくかったとしても、20年、30年、50年経っても「読む価値があるもの」を目指しています。
今、あらゆるコンテンツが「すぐにわかる」「誰でもわかる」を売りにしています。
この連載はその点対称です。
「すぐにはわからない」でも「じっくり読めば誰でもわかる」
是非、とは言えません。
ですが、他には無い価値のある文章であることは間違いありません。
お時間あるときに挑戦してみてください。