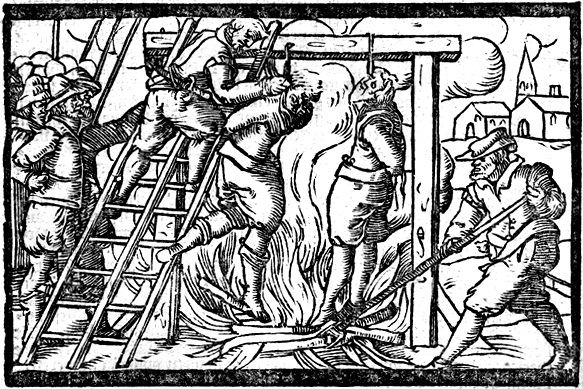それにしても三浦先生の手記から察するに大学というところは職場としてはかなりインタレスティングでエキサイティングなところで、到底自分がそこにマッチして幸せに生きられるとは思えない。
急いで付け加えておくと、自分が知る(所属したところも含めて)一般企業も似たりよったりであって、内部での政治抗争やら嫉妬やら足の引っ張りあいやら無責任やら、大学という組織と同じくらいキュートでセクシーな場所だ。
ある時、もう亡くなられた珠理先生が、加藤さんそんな尖っていては就職出来ないよとおっしゃられたのだが、なんだよ珠理先生のほうが尖りまくってたんじゃないですかと、この本を読み終えた今では言いたくなる。
実は、あまり知る人はいないが、自分は仕事の場では極めてフレンドリーで心が広くて忍耐強くて、どうしても必要だという時以外は決して怒る(ふりをする)こともない。何でも笑顔で引き受けてすぐに仕上げて戻してくれる、大したやつなのだ。
たとえば以前に某社のプロジェクトでご一緒した人と後に飲みに行く機会があり、そのときにSNSでしか私を知らない他の人たちがまるで私をヤバい人みたいに捉えていたので
「私、会議でもなんでも怒ったことなんか無いですよね?」
と声をかけて
「そうですよ。加藤さんは優しいです」
という貴重な証言を即答でもらったことがある。当たり前だ。地位や権力が無くてついでに人間性もクズだったら楽しく健康的に生きていくことは難しいではないか。
だが、三浦先生の手記を読む限りでは、大学という職場で求められているのはウラオモテを使い分けられる人である。オモテでは常識人のふりをして、ズルいこと汚いことをウラで「やれる」人間だ。それならば表と裏が逆になっている「裏では優しくていい人」が入るべき場所ではなかろう。私は少なくともズルいこと汚いことは裏でも表でも「やれない」からだ。
私が立派な、ウラオモテの無いお人柄だと思っている間々田先生、三浦先生、じゅり先生、永見先生、佐々木先生、野谷先生などが苦労しておられたということは、「ウラオモテの無い人」でもしんどい場所なのだから。