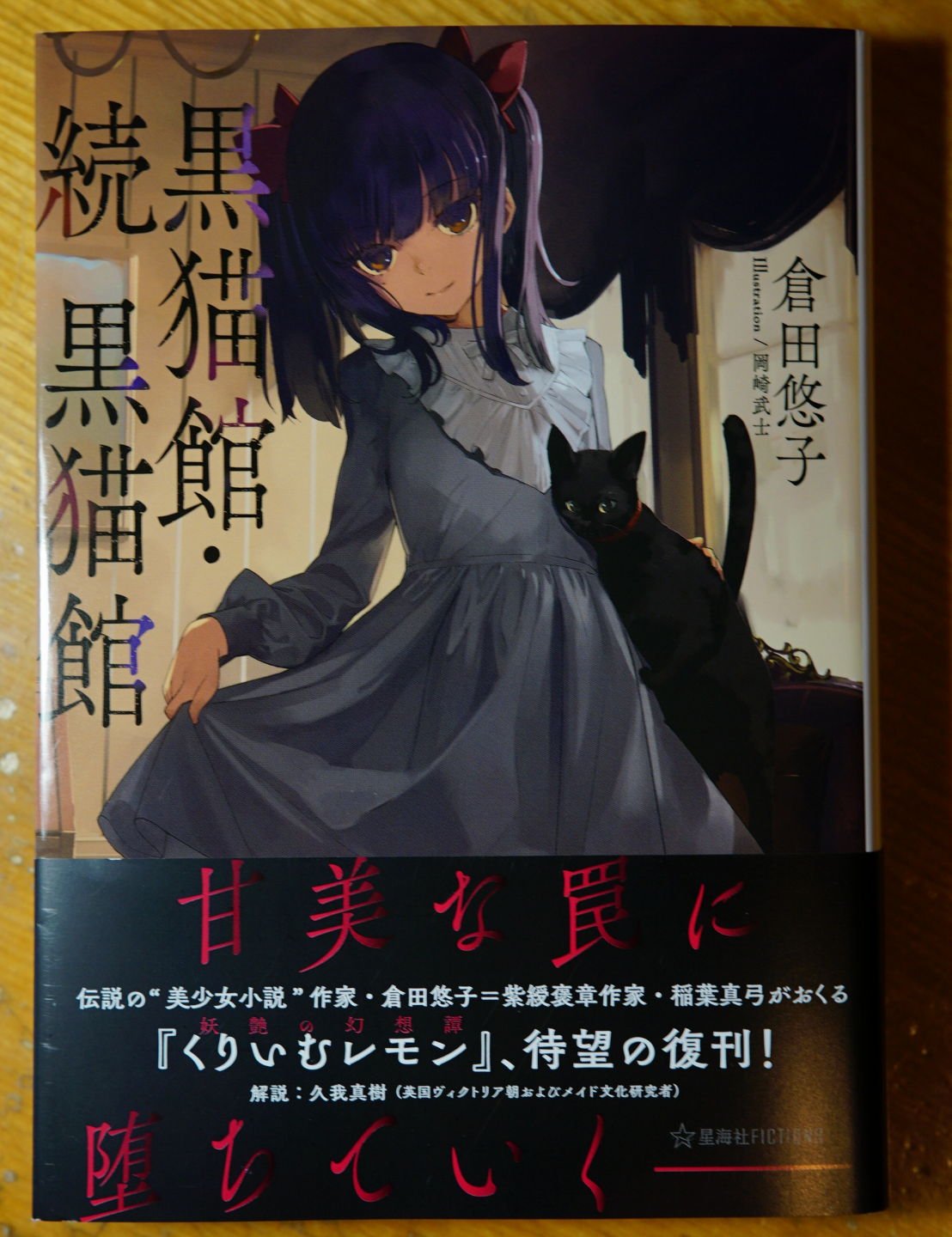そういえば今年が最後となったキヤノンの写真新世紀、過去30年間の大賞受賞者のその後を調べてみたことがあるのですが、写真新世紀受賞がキャリアのハイライトになって、その後は行方知れずの人がいっぱいいて驚きました。
一応、インターナショナルなコンペで賞金額もかなりのものなんですが。
客観的データを見るとJuryも大半が日本人で、特に最初の20年間はJurorのほとんどが大和民族の中高年男性。受賞者もほとんど全て大和民族というコンペだったので、外国人から見ると日本のローカル色がきつすぎるコンペだったのでしょうか。
主催者がCANONで高額賞金で30年間やったわりには、大賞受賞者がその後、世界のアート/写真のシーンで大活躍という事例が多分一つも無かったんですよ今の所。写真新世紀。これから凄い活躍する人が現れる可能性はもちろんありますが。
その理由が社会学的に気になりました。
以下はあくまでも仮説ですが、飯沢耕太郎とか荒木経惟といった、かなり狭い地理的範囲で強力な権威・権力を持つJurorの趣味が強く反映された流れが最後まで続いたということかなとは思います。プロヴォークのアレブレボケから飯沢耕太郎提唱のガーリーフォト、飯沢耕太郎提唱で荒木経惟が繁栄を謳歌した「私写真」みたいなのが最後まで選ばれ続けたような印象が強いです。あの手の作風って日本国内では評価されるけど、外国のInternational Photo Prizeでは傍流もいいとこですからね。