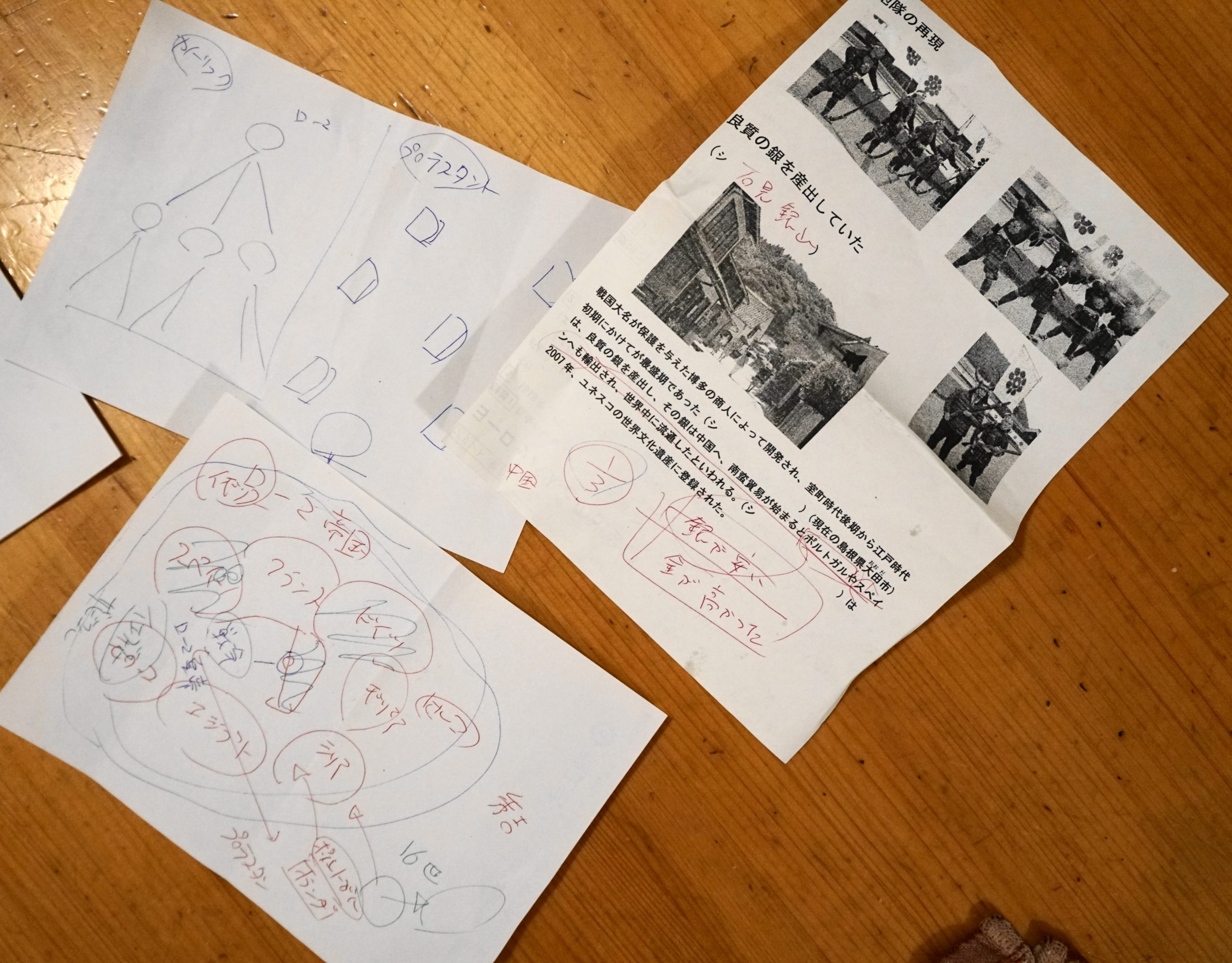今日は応仁の乱から戦国大名の成立までを、権力の配置と作用形態という2軸で息子にレクチャー。
応仁の乱は日本史の中でも最も意味不明なビッグイベントだけれど、武家政権を中央集権型と地方分権型に分けた上で、それが決定的に地方分権型に振れるきっかけとしての、全国的な学級崩壊と思えと説明。
学級崩壊に参加している最中の子供が「自分は今、学級崩壊に主体的に参加している」という意識を持っていないのと同じで、応仁の乱に参加していた連中も、自分たちが何をやっているのかはさっぱり理解していなかったけれど、とにかく日本中で隣の奴と戦う雰囲気だったから、応仁の乱は誰にも意味がわからない戦いだったと。とにかく日本中がグダグダになったんだぞと。
何となく理解は出来たらしい。
同じ「中央集権から地方分権への移行」という枠組みを使えば守護大名(中央にぶら下がっている)から戦国大名(中央ガン無視で自分で法律を作る奴ら)への地方軍閥の移行も理解出来る。守護大名は一応は中央の権力(この場合は鎌倉時代の武家政権が設定した守護公権)を立てるような顔をしていたが、応仁の乱で「将軍」を中心とした全国組織が学級崩壊したから、戦国大名は勝手に法律(分国法)を作って縄張りを支配するようになった。
国一揆や一向一揆も、権力がどこにどのように移動したかということを考えれば良い。守護大名や戦国大名のような大ボスが居ない、つまり権力がもっと細かく分散されている状態だ。そして国一揆と一向一揆の違いは「国レベルのストライキをやったときに、どんなキャッチコピーでストを打ったか」で理解出来る。俺たち山城の国の仲間(国人)というキャッチコピーを使うか、俺たち一向宗仲間というキャッチコピーを使うかの違いだ。
「一向宗じゃない人はどうしたの?」
「そんなもんヤバいから逆らえるわけがない。ちなみにお前も半分は一向宗だ(父方の祖母と母方の祖父がいずれも越中一向宗)」
「まじか」
「まじだ」
「キリスト教の話ばっかじゃなくてそういう話もやれば良かったのにな」
こうやって教えれば、ある国の歴史の動きが、権力の集まっている場所とそのはたらき方の変化と対応していることがわかるし、そういう視点で地域や国家を見るスキルが身につけられれば、それは現代や未来の社会をどう理解するのかにもダイレクトに役立つ。これが歴史を学ぶことの効用の一つだ。
それにしてもいまだに中学の歴史の教材って穴埋め暗記ドリルなのね。これは教材作ってる連中がそもそも歴史教育で何をしたいのか深く考えていない、中身空っぽな連中だからなんだろうなあと思ってしまった。