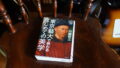現代アート、デカけりゃ良いってもんじゃないという投稿を見てふと気になったこと。
外国はどうか知りませんが、日本の場合、江戸時代に「やたらとデカいスカルプチャー」「半分悪ふざけみたいなスカルプチャー」が大流行していたという歴史があります。
その舞台になったのは、江戸ならば浅草浅草寺、両国回向院、両国橋西詰めの広小路。
名古屋だったら大須の七寺。
これらの場所は日本各地の寺社がメンテナンス費用を集めるためのイベント「出開帳」のベニューでもあったのですが、それ以外に籠細工といって竹の籠で巨大なスカルプチャーを作って展示したり、「とんだ霊宝」というんですが、海産物の干物で仏像を作って展示するというイベントも盛んに開かれていました。
今で言えば出開帳は欧米の有名美術館のコレクション展、籠細工や「とんだ霊宝」は映え重視系の現代アートの企画展と思えばだいたい当たりです。
籠細工では動物や仏などが、高さ数メートルというサイズ感で盛んに作られました。
「とんだ霊宝」は画像検索していただければ納得と思いますが、昨今のイミフな現代アートの中に混ぜても違和感ゼロです。
曲芸や生人形(リアルに造形された等身大の人形。モンスターの生人形もあった)も大人気でした。
浅草、両国で展開されていたその種のスペクタクルが明治になって上野に移り、博覧会、国立博物館、西洋美術館、東京藝大、都美術館、上野の森美術館、上野動物園・・・という、今の上野のインフラが整備されていったわけです。
その辺の話はメディア論の博覧会の辺りで習うのかな? 習わないのかな?
スペクタクルについてはギー・ドゥボールのスペクタクル論がシチュアシオニストの思想の中で展開されているので、さすがに美大や藝大でも習うと思いますが。
定期的に画像バズする巨大現代アート作品、風船でもぬいぐるみでもプラでも石でも同じですが、「これって200年前に両国広小路で流行ってたやつと同じだよなあ」と(個人的に)感じる代物は、多いですね。